
ホーム > 早稲田大学モノグラフ >
早稲田大学モノグラフ21
明治戯作の研究
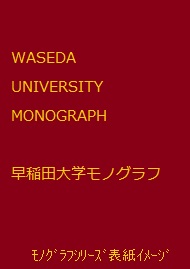 |
|
詳細は、下記からご覧ください。
明治戯作の研究―草双紙を中心として― 目録
起語
序章明治期草双紙の名称を辿る
―所謂明治式合巻と東京式合巻なる呼称の起原をめぐって―
第一章戯作者の転身―仮名垣魯文の場合―
はじめに
第一節魯文と横浜を繋ぐ人々
第二節『胡瓜遣』の正体
第三節『蛸入道魚説教』と『窮理外伝』
―教憲発令後の魯文―
第四節所謂「著作道書キ上ゲ」をめぐって
第二章『鳥追阿松海上新話』の出現まで
はじめに
第一節西南戦争と草双紙
―『鳥追阿松海上新話』の出現をめぐって―
第二節『鹿児島実記一夕話』と『鳥追阿松海上新話』
―大倉孫兵衛の戦略―
第三節『鳥追阿松海上新話』の成立
―連載と草双紙のはざまで―
第四節『鳥追阿松海上新話』の読者の成立
―新聞の宣伝効果―
第三章『鳥追阿松海上新話』につづくもの
はじめに
第一節『夜嵐阿衣花廼仇夢』における成立と趣向の検討
第二節『高橋阿伝夜刄譚』初編における諸問題
―書誌とジャンルを中心に―
第三節連載「お伝の咄」と草双紙『東京奇聞』との其名も高橋
毒婦の小伝
関係の検証
第四章つづきものの形成過程
はじめに
第一節「仮名読新聞」における明治九年の連載に対する
再検討
第二節つづきものと西南戦争
第三節「金之助の話説」の人気をめぐって
―大阪という視点も含めて―
第四節つづきもの論序説
―「大阪」新聞・大坂日報」を中心に― 「
第五章高畠藍泉をめぐって
はじめに
第一節藍泉と大阪―作家への道―
第二節『巷説児手柏』における藍泉自画像
第三節藍泉の作風形成
―「梅柳新話」から『梅柳春雨譚』へ―
第四節『(岡山紀聞)筆の命毛』の成立とその意義
第六章活版草双紙の生成
はじめに
第一節京阪活字版戯作の動向
第二節活版草双紙の誕生
―大阪版より藍泉の独自性に及ぶ―
結び
初出一覧
跋文


