
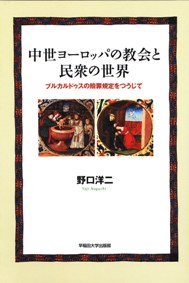 |
中世前半期のヨーロッパでは、「贖罪規定書」と呼ばれる、罪を償う方法を示した手引書が数多く作られ流布していた。それには、殺人、偽誓、近親相姦、偶像崇拝、窃盗、不倫などの重大な罪から、非情な態度、教会でのマナー違反、セクハラ、風呂場で女性の裸を見ることなどの微細な罪にいたるまでのさまざまな罪と、それにたいする償い(パンと水による断食)が、具体的かつ詳細に述べられている。本書は、11世紀初頭に編纂された、その代表的で最も包括的な規定であるヴォルムス司教ブルカルドゥスの規定を取り上げ、それをつうじて、この時代の重大な罪の種類や、民衆教化にたいする教会の政策的意図などを検討するとともに、これらの規定から読み取れる当時の民衆の生活や思考、文化などの一面を明らかにしようと試みている。巻末には、この規定の「試訳」が付されており、史料に直接触れることによって、歴史にたいする興味をより一層深めることができるであろう。
※こちらの書籍の機関向け電子版は、丸善雄松堂Maruzen eBook Library および紀伊國屋書店Net Libraryにて、購入することができます。詳細は各社ホームページをご覧ください。
また、個人向け電子版については、丸善雄松堂の冊子・電子書籍販売サイト「Knowledge Worker」にて購入することができます。詳細は同サイトホームページをご覧ください。
元早稲田大学理事、早稲田大学名誉教授。西洋中世の宗教政治史・文化史を専攻。
著 書:『グレゴリウス改革の研究』(創文社、1978)『中世ヨーロッパの異教・迷信・魔術』(早稲田大学出版部、2016)。
訳 書:フリシュ『叙任権闘争』(創文社、1972)、ハスキンズ『十二世紀ルネサンス』(同、1985)、ヴェルジェ『入門 十二世紀ルネサンス』(同、2001)、ヴェルジェ『ヨーロッパ中世末期の学識者』(同、2004)、他。
はじめに
第1章 新しい贖罪規定の出現とその展開
一 古代の贖罪規定と新しい贖罪規定の出現
二 新しい贖罪規定の展開
三 贖罪規定の利用とその効果
第2章 ブルカルドゥスの『教令集』と贖罪規定「矯正者・医者」
一 ブルカルドゥスと『教令集』
二 ブルカルドゥスの贖罪規定の素材とテキスト
三 「矯正者・医者」の構成
四 いかなる罪が問題となっているか
五 何が重大な罪か
第3章 贖罪の方法・期間および代償方法
一 贖罪の方法と期間
二 パンと水による贖罪に代わる方法
第4章 中世における民衆の世界
一 景観と生活の枠組み
二 迷信(異教的伝統、魔術)―魔術的世界観
三 結婚・離婚・性的行動
四 食べ物と衛生
五 男性中心の社会
むすび
注
【試訳】ブルカルドゥス『教令集』第19巻「償いについて」第1~5章
あとがき


