
ホーム > 新刊案内
新刊案内
田原 加奈子 著
A5判 248ページ / 本体:5,000円+税(2024年11月29日発売)
歌合は和歌行事として平安時代の貴族社会で始まり、遊戯的要素が強かったものが様式の変化に伴い、次第に文芸性が高まっていった。新たな展開を見せたのは『古今和歌集』の成立後ほどない村上朝期(946〜967年)。この勅撰和歌集の残像のなか、歌合の表現は醸成されていった。これらの発展には何が寄与したのか。女集団たる後宮と、男集団たる内裏・臣下の歌合の様相にこそ鍵がある。村上朝前後で和歌表現はどのように展開していくのか。それぞれの歌合の性質に寄り添い、歌合史の視点から文学的な躍動の始まりを村上朝期に見出す新たな表現論。
大日方 純夫 著
新書判 304ページ / 本体:1,050円+税(2024年11月25日発売)
1882(明治15)年10月、早稲田で東京専門学校が開校した。文明開化が起こり外国の文書が多く流入していた時代に、邦語(日本語)教育を提唱したのが、東京専門学校設立に参加した小野梓だ。これは「学問の独立」を目的としたもので、のちに東京専門学校が早稲田大学になった際に教旨に掲げられた。小野梓は大隈重信のブレーンとして、大隈を党首とする立憲改進党を立ち上げ、自由民権運動へ身を投じた。歴史のうねりの中、日本社会の変革をめざし33年10カ月の生涯を走り抜けた。小野梓の思想はどのように育まれ、実践へうつされていったのか。早稲田の建学に照準を定めながら、最新の研究成果を新資料とともに探る。
原口 厚 著
新書判 252ページ / 本体:1000円+税(2024年11月15日発売)
あなたは〈何を伝えたい〉のか――。
〈ヤングケアラー〉〈エッセンシャルワーカー〉などカタカナ語の安易な横行。責任ある言動を放棄し、心地良い〈ポエム〉ばかりを口にする政治家たち。〈ご確認ください〉〈見直し〉といった言葉の決まり文句化……。ますます貧困化が進む私たちの日本語。戦前から現代にいたる社会・教育を振り返りながら原因を探るとともに、日本人が〈理と言葉による意見展開〉ができるようになるための対応策を考える。
塚原 義央 著
A5判 240ページ / 本体:5,000円+税(2024年10月31日発売)
古代ローマ時代、法学者は法の重要な担い手だった。「法の民族」として精緻な法制度を作り上げ、近代法の形成にも多大な影響を与えた。本書では、ローマ法学が最も隆盛を迎えた帝政期において、その時代を代表する法学者の一人であるケルススに焦点をあてる。ケルススは「法は善および衡平の術である」をはじめとする法格言を残し、ローマ皇帝の顧問会メンバーとして施策を支えた。それらの法格言を多角的に分析し、ケルススと同時代の法学者であるユリアヌスの法学と比較し、帝政期ローマの法学者像を導き出す。法文を読み解くことで古代ローマ社会の実態にふれられる法制史。
柴田 元幸 編
新書判 212ページ / 本体:900円+税(2024年10月18日発売)
国境やジャンルを越えて響き合う文学のインスピレーション。
村上春樹が開いた扉とは何か――2023年10月、各国から小説家や芸術家が集い、現代文学と表現の最前線を熱く語り合った。国際シンポジウム(国際交流基金主催・早稲田大学国際文学館共催)を再現!
柴崎友香、チョン・イヒョン、ブライアン・ワシントン、アンナ・ツィマ、呉明益――5人の作家の作品を抜粋して特別収録。
河野 勝 著
新書 236ページ / 本体:900円+税(2024年10月18日発売)
アメリカは、独立・建国以来、自由という概念を存立基盤に据えてきた。その国歌には、戦争を経て自由を勝ち取った誇りが刻まれている。では、アメリカに暮らす普通の人々は、日常生活の中で、自由をどのように感じ、自由について何を悩み、自由をいかに実践しようとしてきたのか。本書は、ボブ・ディラン、ジョニ・ミッチェル、リッチー・ヘヴンス、イーグルス、ニール・ヤング、マルティナ・マクブライドなどによるポピュラー音楽の作品を題材に、その軌跡を辿る。人々の心を揺さぶってきたのは、人種差別への抵抗、政権への批判、社会的弱者への眼差し、家庭内暴力の告発、「本当の自分」を生きることへの切望を表現した、数々の名曲である。実証政治学者として欧米でも高く評価される筆者が、独自の歌詞テキスト分析や現役ミュージシャンへのインタビューなどを織り交ぜ、アメリカの自由を論じる。
坂牛 卓 / 平瀬有人 著
新書判 296ページ / 本体:1,000円+税(2024年9月30日発売)
本書は、第一線で活躍する二人の建築家が、さまざまな芸術における“窓(フレーム)的表現”を参照しながら、それが私たちの暮らしや世界観と密接に結びついていることを、建築家としての現場での経験をもとに明らかにし、「世界」と「窓」とをめぐる従来の議論に建築論的転回をもたらさんとする野心的な論考である。演劇(プロセニアムアーチ)や絵画(額縁)、映画(フレーミング)など、異なる表現における「窓」の役割を分析するいっぽうで、風景を切り取るフレームとしての窓、建物の内外をつなぐ通路としての窓、建物の内部で隔てられた空間同士をつなぐ窓といったように、建築における「窓」の機能についても、独自の視点から多角的な分析を加える。その目線は、近代建築の超克まで見据えており、建築論や都市論の読者はもちろんのこと、メディア論や表象文化論の読者にも楽しんで頂ける、奥の深い内容となっている。
Tomohiro Sakai 著
A5判 396ページ / 本体:7,000円+税(2024年9月20日発売)
分析哲学では外在主義がほぼ定説となっている一方、チョムスキー以降の言語学では内在主義が当然視されている。両主義の間には明白な対立があるにもかかわらず、哲学者が現代言語学の研究に言及することはほとんどなく、逆に言語学者が外在主義に言及することもほとんどない。
外在主義が「言語表現は外的環境の事物を指示し、文は真理値をもつ」ことを前提とするのに対し、チョムスキーは「意味の理論にとって指示や真理の概念は無用である」との立場をとってきた。しかしながら認知言語学はチョムスキー派言語学と異なり、言語使用者と外的環境の相互作用が意味と概念の成立基盤をなすと考える理論であり、外在主義と無関係ではありえない。
外在主義の想定と認知言語学の想定の両立可能性を仔細に検討し、哲学と言語学の架橋を図った画期的研究。※全編英語
Externalism is the philosophical thesis that meaning and mental content are partly dependent for their individuation on one’s social or physical environment. If externalism is true, then two speakers who are molecule-for-molecule identical may nevertheless have different thoughts and mean different things by employing exactly the same word forms. Externalism and its implications have not received sufficient attention in the linguistics literature.
The goal of this book is to investigate the relationships between externalism and cognitive linguistics. Human cognition is biased toward both the internalist conception of linguistic meaning and the externalist conception of natural kinds. Neither bias is rooted in reality. Social externalism coheres with cognitive linguistics. Physical externalism, by contrast, is incompatible not only with cognitive linguistics, but also with biology, chemistry and the philosophy of science. Nevertheless, the physical externalist intuition can be accommodated by the cognitive linguistic apparatus.
村松 聡・宮田 裕光・小村 優太 編著
新書判 418ページ / 本体:1,300円+税(2024年9月6日発売)
心と身体はどのような関係なのか――。この問いは古来より人々に探求されてきた。心と身体は異なるものなのか、あるいはどのようにつながっているのか。心理学、哲学、仏教研究、東洋思想、文化史、文化人類学、教育学において、それぞれの視点から心と身体のつながりを問い直す。異分野間を横断する13章が新たな地平を切り拓く。人間観が深まる、心身論の最前線。
劉宋・范曄 著 / 唐・李賢 注 / 渡邉 義浩 訳
文庫判 564ページ / 1,300円+税(2024年8月9日発売)
大好評の「後漢書」シリーズ第5巻に当たる本書では、臣下の伝記を収めた「列伝」の1巻目として後漢初期の英傑35人の伝記を収録。動乱の時代を生き抜いた、二千年前の洞察と智謀とが克明に綴られる。
【収録人物】
劉玄、劉盆子、王昌、劉永、龐萌、張歩、李憲、彭寵、盧芳、隗囂、公孫述、斉武王劉縯、趙孝王劉良、城陽恭王劉祉、泗水王劉歙、安成孝侯劉賜、成武孝侯劉順、順陽懐侯劉嘉、李通、王常、鄧晨、来歙、鄧禹、寇恂、馮異、岑彭、賈復、呉漢、蓋延、陳俊、臧宮、耿弇、銚期、王覇、祭遵




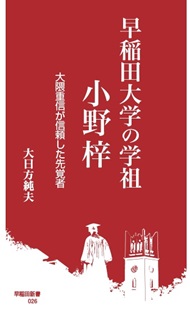
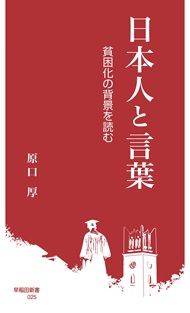

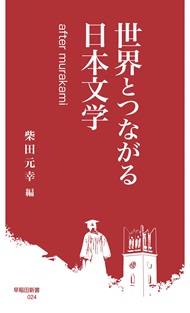
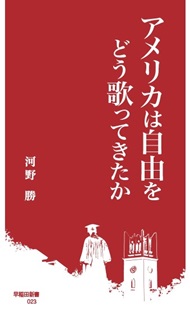


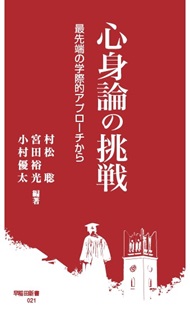
![写真:後漢書 列伝[一]](/bookimg/978-4-657-24004-0.jpg)