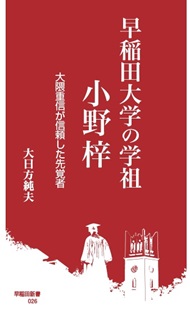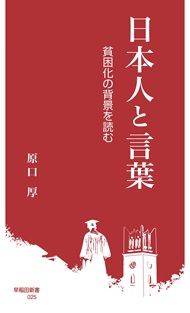ホーム > 新刊案内
新刊案内
ジョージ・リッツア 著 / 正岡 寬司 訳
文庫判 688ページ / 本体:1,800円+税(2024年12月23日発売)
2008年10月に刊行し大好評を得た同名単行本が、満を持して文庫化! マックス・ウェーバーの近代合理化理論の現代版として展開される脱人間化社会の理論「マクドナルド化」。その骨子は、「効率性」「計算可能性」「予測可能性」「制御」の4つの次元にあったが、本書では原書が刊行された2004年当時の時代的要請に応え、「合理性のもたらす非合理性」という新たな次元についても検討が加えられている(7章)。さらには、グローバル化(globalization)が進行するなか、世界の均質化が進むいっぽうで新たな地域性も生まれるという一見矛盾する状況に対し、リッツアは「グローカル化(glocalization)←→グロースバル化(grobalization[リッツアによるgrowthからの造語])」と「存在(something)←→無(nothing)」という2つの座標軸を用いながらユニークな分析を加えたうえで、脱人間化社会に対する抵抗を試みる――真に人間らしい社会を希求する人びとにとって必読の書。
山本 英子 著
A5判 248ページ / 本体:5,000円+税(2024年12月20日発売)
経済学を学問として認識した18世紀後半のフランス絶対王政期の活発な議論の中に重要な論客として関わっていた経済学者グラスラン。先駆的な主観価値理論にもとづく新しい市場社会を描き、農業を中心とする形而上学的な国家思想を説くフィジオクラシーに対し、グランスランは主観価値理論、土地所有交易論、累進的消費税案をもって批判する一方で、フランス東部の都市ナントの大規模な開墾と都市開発をも成功させた。国内で初めてグラスランの経済思想を追究した一書。経済学史におけるグラスランの存在感を際立たせる。
瀬川 至朗 編著
四六判 248ページ / 本体:1,800円+税(2024年12月13日発売)
権力や権威に屈することなく問題の本質を追うこと、ほかのメディアが報じなくてもニュースを伝え続けること、固定化した社会に諦観せず小さな声に光を当てること――社会を動かしたジャーナリストたちの軌跡をたどる。統一教会と政界の癒着、裁判所の事件記録廃棄問題、PFAS汚染、精神科病院の「死亡退院」、南米アマゾンの「水俣病」、新型コロナワクチンの健康被害、性加害問題において、どのような視点を持ち、取材、調査、報道をしていったのか。早稲田の人気講座「ジャーナリズムの現在」の講義録の最新版。
濱本 卓司 著
B5判 356ページ / 本体:9800円+税(2024年12月13日発売)
「耐震設計の父」「塔博士」として知られる早稲田大学教授・内藤多仲。彼が同大学理工学研究所教授・那須信治とともに、戦後まもない時期から約20年間にわたって、数多くの建築物のほか、鉄塔・インフラ施設・タンク等の工作物の振動計測を行い、構造健全性や耐震診断を評価した103件の「診断カルテ」を紹介する。
内藤らの活動は、現在実用化が進みつつある建築物及び土木構造物の構造ヘルスモニタリング技術の先駆けと言える先端研究であった。しかし、その研究内容の全体的意義と学術的価値が評価される機会はこれまでほとんどなかった。
本書は、早稲田大学内藤多仲記念館資料室に残る内藤と那須が残した膨大な資料を再発掘し、少子高齢化、人口減少、空き家問題などが深刻化する日本社会において、今後必要となる構造物の診断技術に有効な教訓を読み取ることを目的とするものである。
◆本書掲載の診断カルテについては、こちらの「ウェブサイト」より、
ほぼオリジナルの形を閲覧することができます。
閲覧をご希望の方は下記フォームにご登録ください。
閲覧に必要なIDとパスワードをお送りいたします。
劉宋・范曄 著 / 唐・李賢 注 / 渡邉 義浩 訳
文庫判 676ページ / 本体:1,500円+税(2024年12月9日発売)
大好評「後漢書」シリーズ第6巻は、臣下の伝記を収めた「列伝」の2巻目。初代皇帝の光武帝から、2代・明帝、3代・章帝、4代・和帝までに仕えた、後漢初期の能臣たちの伝記を収める。
たとえば馬援。62歳のとき、武陵五溪蛮討伐の出陣を願い出て光武帝に制止されるも、それを振り切り馬に飛び乗る。その姿を見た光武帝が笑って曰く、「矍鑠(かくしゃく)としているな、この翁は」。元気な老人を形容する「矍鑠」の典拠になったという。さらには竇憲。和帝即位の翌年、南匈奴を率いて北匈奴を破ると、北匈奴が西進。その後裔が、やがてヨーロッパを脅かすフン族になったとされる。
中国大陸を縦横無尽に、壮大なスケールで活躍する英傑たちの物語。
【収録人物】
任光、李忠、万脩、邳彤、劉植、耿純、朱祐、景丹、王梁、杜茂、馬成、劉隆、傅俊、堅鐔、馬武、竇融、馬援、卓茂、魯恭、魏覇、劉寛、伏湛、侯覇、宋弘、蔡茂、馮勤、趙憙、牟融、韋彪、宣秉、張湛、王丹、王良、杜林、郭丹、呉良、承宮、鄭均、趙典、桓譚、馮衍、申屠剛、鮑永、郅惲、蘇竟、楊厚、郎顗、襄楷ほか。
田原 加奈子 著
A5判 248ページ / 本体:5,000円+税(2024年11月29日発売)
歌合は和歌行事として平安時代の貴族社会で始まり、遊戯的要素が強かったものが様式の変化に伴い、次第に文芸性が高まっていった。新たな展開を見せたのは『古今和歌集』の成立後ほどない村上朝期(946〜967年)。この勅撰和歌集の残像のなか、歌合の表現は醸成されていった。これらの発展には何が寄与したのか。女集団たる後宮と、男集団たる内裏・臣下の歌合の様相にこそ鍵がある。村上朝前後で和歌表現はどのように展開していくのか。それぞれの歌合の性質に寄り添い、歌合史の視点から文学的な躍動の始まりを村上朝期に見出す新たな表現論。
大日方 純夫 著
新書判 304ページ / 本体:1,050円+税(2024年11月25日発売)
1882(明治15)年10月、早稲田で東京専門学校が開校した。文明開化が起こり外国の文書が多く流入していた時代に、邦語(日本語)教育を提唱したのが、東京専門学校設立に参加した小野梓だ。これは「学問の独立」を目的としたもので、のちに東京専門学校が早稲田大学になった際に教旨に掲げられた。小野梓は大隈重信のブレーンとして、大隈を党首とする立憲改進党を立ち上げ、自由民権運動へ身を投じた。歴史のうねりの中、日本社会の変革をめざし33年10カ月の生涯を走り抜けた。小野梓の思想はどのように育まれ、実践へうつされていったのか。早稲田の建学に照準を定めながら、最新の研究成果を新資料とともに探る。
ユッカ・ハッキネン 著/河合 隆史 訳
A5判 244ページ / 1,800円+税(2024年11月22日発売)
「アメリカ人の46%が、ビル・ゲイツがCOVID-19ワクチンに追跡装置を含めたと信じている⁉」
「フランス人の48%が、グローバルエリートがメディアと共謀して、ヨーロッパの白人をイスラム教徒の移民と置き換えていると信じている⁉」
「ポーランド人の30%が、ユダヤ人は秘密裏に世界征服を企んでいると信じている⁉」
――人はなぜ陰謀論に惹かれるのか。その理由について、海外の事例を多数挙げながら脳科学の見地から分析する。そして、陰謀論が一部の人々に起こる特別な現象ではなく、すべての人に起こりうることを脳機能の観点から明らかにする。
現代はSNSの発達などによって、陰謀論が広まりやすい社会的状況にある。これを防ぐには正確な情報の普及が大切なことはもちろん、私たち一人一人が自身の弱点を理解し、自らの思考に対して批判的検討をすることが重要である。本書の出版はその要請に応えるものである。
「現代を揺るがす「陰謀論」の起源を明かす名著。必読です!」茂木健一郎(脳科学者)
原口 厚 著
新書判 252ページ / 本体:1000円+税(2024年11月15日発売)
あなたは〈何を伝えたい〉のか――。
〈ヤングケアラー〉〈エッセンシャルワーカー〉などカタカナ語の安易な横行。責任ある言動を放棄し、心地良い〈ポエム〉ばかりを口にする政治家たち。〈ご確認ください〉〈見直し〉といった言葉の決まり文句化……。ますます貧困化が進む私たちの日本語。戦前から現代にいたる社会・教育を振り返りながら原因を探るとともに、日本人が〈理と言葉による意見展開〉ができるようになるための対応策を考える。
塚原 義央 著
A5判 240ページ / 本体:5,000円+税(2024年10月31日発売)
古代ローマ時代、法学者は法の重要な担い手だった。「法の民族」として精緻な法制度を作り上げ、近代法の形成にも多大な影響を与えた。本書では、ローマ法学が最も隆盛を迎えた帝政期において、その時代を代表する法学者の一人であるケルススに焦点をあてる。ケルススは「法は善および衡平の術である」をはじめとする法格言を残し、ローマ皇帝の顧問会メンバーとして施策を支えた。それらの法格言を多角的に分析し、ケルススと同時代の法学者であるユリアヌスの法学と比較し、帝政期ローマの法学者像を導き出す。法文を読み解くことで古代ローマ社会の実態にふれられる法制史。





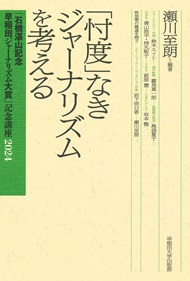

![写真:後漢書 列伝[二]](/bookimg/978-4-657-24011-8.jpg)