
ホーム > 政治経済・法律・ビジネス, 新刊案内, 書評に出た本・受賞した本 > スウェーデンの租税政策
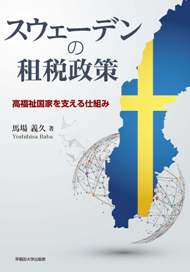 |
【租税資料館賞受賞!】
スウェーデンの高福祉は巨額の税収によって支えられている。巨額税収をあげるためには、課税の公平性を確保しつつ、民間活力を極力阻害しない租税政策が求められる。
1991年の二元的所得税の導入以降のスウェーデンの租税政策を検証し、同国がいかにして社会保障費などの財源を調達しているかを解明する。それは超高齢社会の日本にとっても、大いに参考となるであろう。
【訂正情報】本書99頁の図4-8につきましては、誤りがございました。お詫びのうえ、下記の通り訂正させていただきます。
図4-8(p.99)訂正.pdf
早稲田大学名誉教授,(一社)総合政策フォーラム特別研究員。
1949年生まれ。一橋大学経済学部卒業,同大学大学院経済学研究科博士課程満期退学。関東学院大学専任講師・助教授,長崎大学助教授・教授,早稲田大学政治経済学術院教授などを歴任。
主な著書に『所得課税の理論と政策』(税務経理協会),『マクロ経済学と経済制度』(早稲田大学出版部,編著),『二元的所得税の論点と課題』(日本証券経済研究所,共著),『リスクと税制』(日本証券経済研究所,共著),『日本の財政を考える』(有斐閣,横山彰・堀場勇夫・牛丸聡各氏との共編著)などがある。
はしがき
第1章 二元的所得税の誕生
1 本章の課題
2 総合所得税主義下の資産所得税の実際
3 二元的所得税の基本とねらい
4 事業所得税制――二元的所得税のアキレス腱
第2章 普遍的負担と再分配――勤労所得税の役割
1 本章の課題と構成
2 勤労課税の地位と役割分担
3 勤労所得税の基本的特徴
4 政策的背景・理論的意味
第3章 資産所得税制の再生――改革のメリット
1 本章の課題と構成
2 スウェーデン資産所得税制のしくみ
3 資産所得税制の実態
4 スウェーデン資産所得税制のメリット(1)――比例税率
5 スウェーデン資産所得税制のメリット(2)――包括的損益通算
6 おわりに
第4章 勤労所得税税額控除政策――勤労所得税の変化
1 本章の課題と構成
2 EITC導入の背景とねらい
3 EITC政策の仕組みと特徴――2015年までのシステム
4 EITCによる労働供給増大効果――スウェーデンにおける研究より
5 中高所得層対策とフェイズアウトの導入
6 現物社会保障の財源調達構造の変化
【コラム1】動学的税収変化の算出
第5章 長寿リスクへの対応――年金税制の長所と課題
1 はじめに
2 スウェーデンの年金制度の概観
3 公的年金制度とリスク対応
4 職域年金による公的年金の補完
5 年金税制のしくみと検討
6 結び
第6章 資産保有税は不要か――純資産税の廃止・固定資産税の変容
1 はじめに
2 資産保有税の正当化論と批判論
3 スウェーデンの資産保有税――補完機能の実際
4 純資産税の廃止について
5 固定資産税の改革――地方住宅負担金への変更
6 結論と日本への政策的含意
【コラム2】投資貯蓄口座(ISK)の導入について
第7章 ノルウェー方式の限界――法人税と資産所得税の負担調整
1 はじめに
2 ノルウェー旧方式の限界――インピュテーション法とRISK
3 SITの意義と限界
4 結び――ノルウェー方式の限界の原因
第8章 スウェーデンの模索――新しい法人税の提案
1 はじめに
2 個人段階の負担調整消極論の政策的背景
3 所得型法人税の限界と新しい法人税
4 スウェーデンとACE法人税 vs CBIT
5 スウェーデンの2014年改革案について
第9章 軽減税率は何のために?――消費税の実際
1 本章の課題
2 消費税の基礎理論
3 スウェーデン消費税の税率構造と背景
4 スウェーデン消費税の負担実態
5 軽減税率と税務執行
6 評価と日本への教訓
第10章 税務情報の捕捉システム――徴税・納税の実際
1 はじめに
2 納税者番号制度と住民登録制度のしくみ
3 所得税の徴税・納税システム
4 各税制における税務情報の信頼度
5 租税ギャップ
6 結びに代えて
あとがきに代えて
初出一覧
参考文献
索 引


