
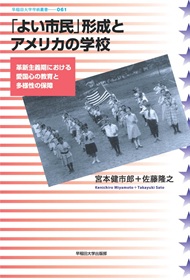 |
1890年代から1910年代、アメリカでは革新主義が潮流となるなか、「よい市民」の形成が試みられていた。子どもひとりひとりを尊重する進歩主義教育が台頭しつつも、一つの国家としての統一が目指されていた時代。「よい市民」形成という壮大な市民性教育の実験は、学校が社会と結びつき、その役割を変容させていきながら行われた。本書では遊び場運動、社会センターとしての学校、コミュニティ・センター運動、国旗掲揚の儀式、帰化プロジェクトの授業などをとりあげ、それらを主導したジョセフ・リー、クラレンス・A.ペリー、ジョン・デューイらの思想とともに、「よい市民」の理念と実態を考察する。対照的な「多様性の尊重」と「愛国心の教育」はどのように結びつき、実践されたのか。著者二人の約20年にわたる共同研究の集大成。
宮本健市郎
1956年生まれ。1986年東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。京都大学博士(教育学)。1990年兵庫教育大学学校教育学部講師。1993年同助教授。2005年神戸女子大学文学部教授。2009年関西学院大学教育学部教授。専門は教育学、教育史、教育方法史、とくにアメリカ教育史。
主な著書に『アメリカ進歩主義教授理論の形成過程:教育における個性尊重は何を意味してきたか』(東信堂)、『空間と時間の教育史:アメリカの学校建築と授業時間割からみる』(東信堂)など。
佐藤隆之
1966年生まれ。1998年早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(教育学)早稲田大学。2000年玉川大学教育学部講師、2005年同准教授。2008年早稲田大学教育・総合科学学術院准教授。2011年同教授。専門は教育思想(アメリカ)。
主な著書に『キルパトリック教育思想の研究:アメリカにおけるプロジェクト・メソッド論の形成と展開』(風間書房)、『市民を育てる学校:アメリカ進歩主義教育の実験』(勁草書房)など。
序 章 アメリカ革新主義期における「よい市民」形成の思想と実態
第1節 「よい市民」の理念と教育
第2節 愛国心の教育と多様性の保障
――考察の方法と範囲
第3節 進歩主義教育運動とナショナリズムの展開
――国民意識の形成と生活様式の画一化
第4節 本書の構成と概要
第Ⅰ部 「よい市民」とはなにか――思想・理念の解明
第1章 ジョセフ・リーにおける慈善とリクリエーションの思想
――アメリカ遊び場協会での仕事を中心に
はじめに
第1節 子ども救済運動――マサチューセッツ公民連盟
第2節 アメリカ遊び場協会の継承と変質
第3節 地域奉仕活動の推進
おわりに
第2章 ジョセフ・リーにおける「よい市民」形成の論理
はじめに
第1節 建設的慈善の思想
第2節 リーの発達観――本能の解放
第3節 「よい市民」の形成――家庭・学校・国家への忠誠心
おわりに――アメリカ的精神としての市民性
第3章 デューイにおける「よい市民」の理念
――読解「教育の根底にある倫理的原理」(1897)
はじめに――デューイの原点
第1節 デューイの市民性教育論を問う意義と課題
第2節 「子どもとしての市民」――家族・仕事・コミュニティ
第3節 アメリカにおける「よい市民」(1)――アメリカの民主主義
第4節 アメリカにおける「よい市民」(2)――ケアする市民,ケアされる市民
第5節 社会を理解する市民――「社会的想像力と概念作用の習慣形成」
おわりに――〈倫理的原理〉が示唆する「よい市民」
第4章 デューイにおける「よい市民」の探求
――「よさの多様性」
はじめに――20世紀初頭から1920年代半ばまでの展開
第1節 「社会センターとしての学校」論における市民性
第2節 労働者としての市民
第3節 民主主義と教育における民主的市民
第4節 市民性論議のなかのデューイ
おわりに――デューイの「よい市民」の展開と多様性
第Ⅱ部 学校は「よい市民」を形成する場となりうるか
――学校になにを期待するか
第5章 アメリカにおける遊び場運動の起源と展開
――子ども救済からリクリエーションへ
はじめに
第1節 遊び場運動の起源――慈善活動への公的支援
第2節 遊び場への公的支援の形態――三つの型
第3節 アメリカ遊び場協会の結成と方針転換
おわりに
第6章 社会センターとしての学校の実験と挫折
――校舎開放からコミュニティ・センターへ
はじめに――問題の所在
第1節 社会センターの思想的起源
第2節 ニューヨーク州ロチェスターの社会センター
第3節 社会センターからコミュニティ・センターへ
――運動の広がりと変質
おわりに
第7章 デューイの社会センターとしての学校における市民形成
――福祉=幸福(welfare)概念に注目して
はじめに
第1節 デューイの社会センターとしての学校論への再注目
第2節 二つの社会センターとしての学校と身体的福祉=幸福
第3節 「意欲的で責任ある市民」の形成
――自由と規律
第4節 交差する身体的福祉=幸福と社会的福祉=幸福
おわりに――社会センターとしての学校の示唆と課題
第8章 社会センターとしての学校における市民性教育の実際
――ニューヨーク市におけるゲーリー・プランの実験
はじめに
第1節 ゲーリー・プランの実際――ニューヨーク市での導入
第2節 身体的福祉=幸福に基づく市民性教育の実際
第3節 ゲーリー・プランに対するデューイの期待とその解釈
第4節 ゲーリー・プランの適応可能性
おわりに――学校における「よい市民」形成の可能性
第Ⅲ部 愛国心・忠誠心の教育が「よい市民」の形成になるか
―― コミュニティ・儀式・授業
第9章 学校によるコミュニティ形成と国民形成
――コミュニティ・センターから近隣住区論へ
はじめに――公教育におけるローカリズムとナショナリズム
第1節 コミュニティ形成論――社会センター運動の目的と実際
第2節 国民形成論――コミュニティ・センター運動の広がり
第3節 アメリカ的コミュニティの探究
――家庭から国家,国家から世界へ
おわりに――コミュニティ・センター運動と市民形成
第10章 アメリカの公立学校における国旗掲揚運動の起源と機能転換
――統合から排除へ
はじめに
第1節 南北戦争の遺産――戦争と愛国のシンボルとしての国旗
第2節 国旗掲揚運動と国旗忠誠の誓い
第3節 国旗敬意法と国旗記念日の制定――多様性の否定
おわりに
第11章 市民性プロジェクトの授業とアメリカ化
――帰化プロジェクトの実際
はじめに
第1節 帰化プロジェクトの目的
第2節 授業の「導入」部――「要の問い」と『帰化法令集』
第3節 授業の「展開」部――法的手続きに関する学習
第4節 アメリカ化とプロジェクトの交差
おわりに
第12章 帰化プロジェクトにおける忠誠心の教育と課題
はじめに――帰化プロジェクトの授業の終末
第1節 帰化プロジェクト第5ステップの構成
――移民の忠誠宣誓を助ける責任
第2節 移民に対する共感の学習
――文学作品を用いた市民性教育
第3節 移民とは誰か――移民の歴史と現在
第4節 移民をめぐる時事問題のディベート
第5節 帰化プロジェクトにおける忠誠宣誓と責任の一解釈
第6節 市民性プロジェクトにおける多様性と愛国心
おわりに
終 章 「よい市民」形成の実態と論理
第1節 ジョセフ・リーの思想と活動
――子ども救済から「よい市民」の形成へ
第2節 クラレンス・A. ペリーの思想と活動
――「アメリカ的生活様式」のための環境整備
第3節 デューイの思想と進歩主義学校における実践
第4節 愛国心と多様性の交差
第5節 残された課題
あとがき
主要参考文献
事項・書名索引
人名索引
英文要旨


