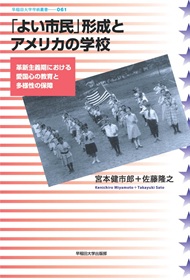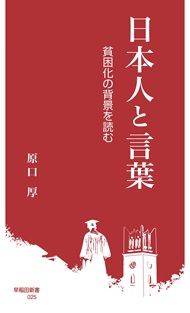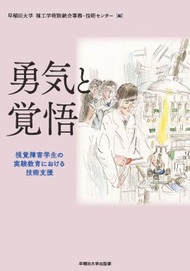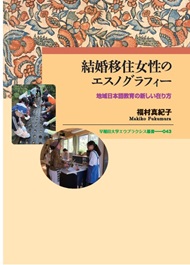ホーム > 社会・教育
社会・教育
早稲田大学台湾研究所 編
B5判 96ページ / 本体:1,600円+税(2025年4月18日発売)
アジアについての研究成果を広く一般の読者に発信するジャーナル、リニューアル第2弾!
特集①は「日台漫画論」。いまや、日本を代表する文化の一つでもあり、重要な輸出産業ともなっている漫画。その日本漫画の影響を汲みながら、WEBを舞台に新たな作品世界を開花させつつある台湾漫画。日本と台湾の漫画のいま・むかしを考えます。
特集②は「学生運動を考える」。不確実な時代の今、学生運動について改めて考えます。歴史上、世界の至るところで、若者たちは主張し行動を起こしてきました。目的や方法、規模や結果の違いはあっても未来のために理想を求めたかれらの姿勢に注目、その事実を無駄にすることなく、理解と教訓を得るために多角的な検証を行います。『レッド』の作者、山本直樹氏のインタビューも掲載!
そのほか、編集長インタビューにデヴィ・スカルノ夫人も登場するなど今号も盛りだくさんの内容です。
宮本 健市郎・佐藤 隆之 著
A5判 418ページ / 定価:7,000円+税(2025年4月10日発売)
1890年代から1910年代、アメリカでは革新主義が潮流となるなか、「よい市民」の形成が試みられていた。子どもひとりひとりを尊重する進歩主義教育が台頭しつつも、一つの国家としての統一が目指されていた時代。「よい市民」形成という壮大な市民性教育の実験は、学校が社会と結びつき、その役割を変容させていきながら行われた。本書では遊び場運動、社会センターとしての学校、コミュニティ・センター運動、国旗掲揚の儀式、帰化プロジェクトの授業などをとりあげ、それらを主導したジョセフ・リー、クラレンス・A.ペリー、ジョン・デューイらの思想とともに、「よい市民」の理念と実態を考察する。対照的な「多様性の尊重」と「愛国心の教育」はどのように結びつき、実践されたのか。著者二人の約20年にわたる共同研究の集大成。
Administration and Technology Management Center for Science and Engineering, Waseda University
A5判 349ページ / 定価:4,000円+税(2025年4月3日発売)
2023年12月に発売し大好評を博した『勇気と覚悟――視覚障害学生の実験教育における技術支援』の英語版。
2019年4月、早稲田大学 先進理工学部に一人の全盲の学生が入学した。小学2年生の時に全盲となった彼女は、筑波大学附属視覚特別支援学校中学部、都立高校を経て、早稲田大学を受験。みごと現役合格を果たしたのである。
はたしてどのようにすれば、全盲の学生に大学の実験科目を履修してもらうことが可能なのか。この課題に中心となって対応したのが、早稲田大学 理工学術院統合事務・技術センターの技術職員たちであった。つねに彼女に寄り添いながら、学内外のステークホルダーたちを巻き込みつつ、高等教育機関として実験科目を通じて彼女に何を伝えるべきか、という根本的な問題意識の下に奔走した彼ら。その現場からの報告。
千葉 美奈 著
A5判 250ページ / 本体:5,000円+税(2024年12月24日発売)
世界的に青少年の早期妊娠やHIV感染が増加するなか、青少年のリプロダクティブ・ヘルスをいかに保護するかが急務となっている。保護にあたって重要なのが包括的性教育(CSE)の取組である。しかしCSEは、それぞれの国における政治的論争や学校現場での支持不足などにより十分に実施できているとはいいがたいのが実情である。
そんななかタイでは、学校を基盤とする質の高いCSEが実現された。なぜタイは成功したのか。同国の学校現場における調査・報告を通じ、効果的な性教育の普及のために必要な方策を考察する。青少年の保健教育に携わる教職員にとって、貴重な示唆に富む一冊。
ジョージ・リッツア 著 / 正岡 寬司 訳
文庫判 688ページ / 本体:1,800円+税(2024年12月23日発売)
2008年10月に刊行し大好評を得た同名単行本が、満を持して文庫化! マックス・ウェーバーの近代合理化理論の現代版として展開される脱人間化社会の理論「マクドナルド化」。その骨子は、「効率性」「計算可能性」「予測可能性」「制御」の4つの次元にあったが、本書では原書が刊行された2004年当時の時代的要請に応え、「合理性のもたらす非合理性」という新たな次元についても検討が加えられている(7章)。さらには、グローバル化(globalization)が進行するなか、世界の均質化が進むいっぽうで新たな地域性も生まれるという一見矛盾する状況に対し、リッツアは「グローカル化(glocalization)←→グロースバル化(grobalization[リッツアによるgrowthからの造語])」と「存在(something)←→無(nothing)」という2つの座標軸を用いながらユニークな分析を加えたうえで、脱人間化社会に対する抵抗を試みる――真に人間らしい社会を希求する人びとにとって必読の書。
ユッカ・ハッキネン 著/河合 隆史 訳
A5判 244ページ / 1,800円+税(2024年11月22日発売)
「アメリカ人の46%が、ビル・ゲイツがCOVID-19ワクチンに追跡装置を含めたと信じている⁉」
「フランス人の48%が、グローバルエリートがメディアと共謀して、ヨーロッパの白人をイスラム教徒の移民と置き換えていると信じている⁉」
「ポーランド人の30%が、ユダヤ人は秘密裏に世界征服を企んでいると信じている⁉」
――人はなぜ陰謀論に惹かれるのか。その理由について、海外の事例を多数挙げながら脳科学の見地から分析する。そして、陰謀論が一部の人々に起こる特別な現象ではなく、すべての人に起こりうることを脳機能の観点から明らかにする。
現代はSNSの発達などによって、陰謀論が広まりやすい社会的状況にある。これを防ぐには正確な情報の普及が大切なことはもちろん、私たち一人一人が自身の弱点を理解し、自らの思考に対して批判的検討をすることが重要である。本書の出版はその要請に応えるものである。
「現代を揺るがす「陰謀論」の起源を明かす名著。必読です!」茂木健一郎(脳科学者)
原口 厚 著
新書判 252ページ / 本体:1000円+税(2024年11月15日発売)
あなたは〈何を伝えたい〉のか――。
〈ヤングケアラー〉〈エッセンシャルワーカー〉などカタカナ語の安易な横行。責任ある言動を放棄し、心地良い〈ポエム〉ばかりを口にする政治家たち。〈ご確認ください〉〈見直し〉といった言葉の決まり文句化……。ますます貧困化が進む私たちの日本語。戦前から現代にいたる社会・教育を振り返りながら原因を探るとともに、日本人が〈理と言葉による意見展開〉ができるようになるための対応策を考える。
甲斐 伊織 著
A5判 270ページ / 本体:4,000円+税(2024年4月5日発売)
大正時代に起きた新教育運動以降、国語教育において学習者が主体的に学ぶ教育思想、教育実践は繰り返し強調されてきた。しかし、そのような立場は、一般化されたものにはならなかった。本書は、単元学習の実践者として広く知られる大村はま(1906~2005)の実践を研究の対象とし、その課題の克服に向けた知見を得ることが目的である。大村国語教室における個別の単元の成立の背景には、大村の教材研究やそれに基づく手引きなど、大村個人の力量によるものと共に、もう一つの要因がある。それは、大村の指導によって教室に蓄積されてきた学習者の学習経験である。本書では、大村国語教室における学習経験の蓄積の復元・考察を通して、今日の国語教室と共通する、主体的な言語活動を成立させる要素や単元相互の関連、および個々の単元が果たす役割について考察する。
早稲田大学 理工学術院統合事務・技術センター 編
A5判 352ページ / 本体:4,000円+税(2023年12月25日発売)
2019年4月、早稲田大学 先進理工学部に一人の全盲の学生が入学した。小学2年生の時に全盲となった彼女は、筑波大学附属視覚特別支援学校中学部、都立高校を経て、早稲田大学を受験。みごと現役合格を果たしたのである。そこで課題に直面したのは早稲田大学であった。はたして、どのようにすれば全盲の学生に大学の実験科目を履修してもらうことが可能なのか。この課題に、中心となって対応したのが、早稲田大学 理工学術院統合事務・技術センターの技術部に所属する技術職員たちであった。彼らはつねに彼女に寄り添いながら、学内外のステークホルダーたちを巻き込みつつ、高等教育機関として、当該の実験科目を通じて彼女に何を伝えるべきなのか、という根本的な問題意識の下に奔走する。その技術部の視点から綴った、現場からの報告が本書である。ダイバーシティやインクルージョンの重要性が叫ばれるなか、視覚障害教育に携わる人たちにとってはもちろん、すべての教育関係者にとって貴重な示唆に富んだ、他に類を見ない一冊である。
福村 真紀子 著
A5判 270ページ / 本体:4,000円+税(2023年12月25日発売)
「日本では何もできない」。夫の国である日本に移住したものの、日本語が自在に操れず、孤立していた子育て中の外国人女性のことばである。出自国と日本との経済格差により弱い立場に置かれることも多く、社会で活躍するチャンスも奪われ、人的ネットワークも築けない。そのような結婚移住女性たちのコミュニケーションの力を、いかに育てればよいのか。日本語教師である著者が立ち上げた、結婚移住女性と日本人女性が交流する親子参加型サークルでの実践研究をもとに、地域日本語教育の在り方を考える。コミュニケーションの力が育つ過程で〈ことばの学び〉がどのように促されるのか、エスノグラフィーを通して浮かび上がらせる。