
ホーム > 書評に出た本・受賞した本
書評に出た本・受賞した本
井口 隆史
A5判 568ページ / 本体 3,000円+税
「日本の野球の父」と敬愛されるその人は自由なキリスト教信仰と愛する妻に支えられ、平和・民主・社会主義の先駆けとして激動の明治・大正・昭和を清冽に生き抜いた理想主義者であった。
イチロー、松井秀喜が大リーグで大活躍し、日本の野球ファンは、なにかとてつもない大きな夢を達成したような気分に浸った。こうした「夢」を、最初に見たのは誰だったろう。明治時代に、それも日露戦争のまっただなかに、早稲田大学の学生プレイヤーたちを引きつれてアメリカに渡り、本場の野球に挑んだ〝元祖・侍ジャパン〟、安部磯雄ではないか。まだ、“お国”ですら外交デビューを果たしたばかりの中、“WASEDA UNIV.”をいち早くアメリカ人に知らしめ、早稲田大学に国際交流の目を開かせたのは、この遠征にあり、実現に尽力した安部にあると言えるだろう。
学生野球の父・安部がいたからこそ、古くは長嶋茂雄、そして斎藤佑樹も神宮のスターとして名を馳せることができたのである。今でも早大野球部は、命日に現役部員が墓参を行う。
しかしながら安部の功績は、野球文化の興隆だけではなく、今の民主党にも繋がる社会主義系の政党の黎明期にその流れを確固たるものにしたことにあり、初期の社会主義の弁士である片山哲・西尾末広など錚々たる政治家が安部のもとを頻繁に訪れていることが夫人の日記を通じて描かれている。安部の体調や日和までをも交えて淡々と書かれている日記に、逆に大正デモクラシーや第二次世界大戦に向かう激昂時代を誠実無比に生きた安部の姿を生々しく感じる読者は多いだろう。
第60回日本エッセイスト・クラブ賞。[外部リンク]
日本図書館協会選定図書。
河西 宏祐 著
A5判 302ページ / 本体 6,100円+税
「広電現象」
2009年、「広電現象」とよばれる社会現象が巻き起こった。広島に本社を置く広島電鉄の労働組合が、この年の春闘において、「全契約社員の正社員化」という成果を獲得したというニュースが全国を駆け巡ったのである。その労働組合の名前は、私鉄中国労働組合広島電鉄支部という。
「第Ⅰ部 混迷」では、約40年間にわたって分裂状態にあった同社の2つの労働組合が統一を果たし、新たな広電支部が誕生した1993年から、経営側にたいする反攻に転じた2002年までの約10年間を扱っている。この約10年間、広電支部は経営側からの激烈としか言い様の無いほどの激しい経営合理化攻勢にさらされ続け、組合内は混迷の極みにあった。
「第Ⅱ部 再生」では、苦境のなかから支部が反転のきっかけをつかみ、2009年の「全契約社員の正社員化」を実現するまでの再生過程を扱っている。
【教科書・参考書指定】 広島大学
#本商品は在庫僅少となっております。[新装版(ソフトカバー)](2012年7月25日発売)のページをご覧ください。
三菱商事株式会社 編/堀口健治・笹倉和幸 監修
A5判 325ページ / 本体 2,600円+税【電子版あり】
最先端のグローバル・ビジネスが見える,わかる。三菱商事で最前線に立つ執行役員,本部長,マネージャーほかによる人気講義の書籍化。現役商社マンの間でも話題沸騰。業界研究・就職活動の決定版。大好評7刷。
【教科書・参考書指定】 早稲田大学商学部、一橋大学大学院商学研究科
【『早稲田学報』1189(2011年10月号)(早稲田大学校友会)の「本と本棚」に書評掲載。評者:藁谷友紀氏(早稲田大学教育・総合科学学術院教授)】
※電子版のご購入にあたっては,各電子書店サイトで詳細をご確認ください:
iBook Store*/アマゾンKindleストア/ebookjapan/GALAPAGOS STORE/紀伊國屋書店/コープデリeフレンズ電子書店/セブンネット/東芝ブックプレイス/VarsityWave eBooks/ひかりTVブック/BooksV/Booklive/honto/本よみうり堂デジタル/楽天Kobo/Reader Store/YONDEMILL
*iPhone/iPadなどのiBooksアプリ、またはiTunes Storeで「早稲田大学出版部」を検索してください。
堀口健治・加藤基樹 編
四六判 / 本体 1,800円+税【電子版あり】
はしがき
「うわ!」横一列に並んで田植えをする学生たちの列が乱れた。ぬかるみに足を取られて転んだ一人を中心に笑顔がはじける。日本の棚田百選に選ばれた新潟県松代の田んぼ(表紙の写真参照)での春のひとコマ。この田植え実習を皮切りに,岩手県田野畑,山形県高畠,寒河江,福井県三国の4か所を実習地とした農山村体験実習が始まる。
「日本の農業が日本の社会とそんなに強い関係にあるとわかって,びっくりしました。・・・日本を理解するためには,日本の農業も理解しなければならないと考えます」(2009年度農山村体験実習報告書・WAVOC刊)。日本の農村を体験した,シンガポールからの留学生の感想である。日本社会の一部であり,国土を広く利用する農山村の役割。実は,参加者の多くを占める都市出身の学生も,シンガポール出身の彼女とほぼ同じ感想を持つ。
何より学生が驚くのは,農村が,そして農家が他者に対して開かれていることである。都市での個(場合によっては孤独の孤)を中心にした閉鎖的な生活に対して,村で体験する家同士が連携し訪問者をも広く受け入れる社会。「地域のつながりが東京にはないものがある。人のやさしさや濃いネットワークに触れて感動した。・・・田舎ということと,農業ということと,人が温かいということと,皆で協力しあって作業をすることとか,・・・改めて地域のネットワークは大切だなと感じた」(2002年堀口教養ゼミ4期生夏合宿報告書)。学生たちは,農村に残る人々の濃密なつながりに一番の衝撃を受ける。
そうした経験は,それを共有した他者との関係にも影響する。この実習を通して学生同士が,学年・学部・専門を越えて親しくなるのも,農村をフィールドとするこの授業の魅力である。さまざまな動機を持った学生たちが共に学び,調査表を共作して農村へ向かう。体験とその振り返りを行いながら,自分を取り巻く社会について深く考える。同じ農山村で農家体験をすることで,まず問題意識を共有する。これがこの授業の「農林業問題入門」としての第一目標である。しかし,学生たちにとっての終わりにはならない。学部や専門を超えた,問題意識を共有する学生たちは,やがて自分自身で学び,行動を起こす。
本書は,そうした動きを,早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(以下,WAVOCないしボランティアセンターと略称)が提供してきた授業科目の経験を通じて紹介する。早稲田が7年にわたって行ってきた都市と農村との往還,その仕組みや成果を,多くの学生,大学関係者,農村の人々に届けたい。
近年,キャンパスから離れた農村や山村における大学生の活動への期待が高まっている。本書は,7年間約400人に及ぶ早稲田生と,農村で立ち上がったボランティアの人々の記憶でもある。この「書」にある先輩たちの「声」が,後に続く学生を農村にいざなう道しるべとなることを願ってやまない。(本文より)
日本図書館協会選定図書。
全国学校図書館協議会選定図書。
【教科書・参考書指定】 早稲田大学オープン教育センター
【『全国農業新聞』第2730号(2011年5月6日・金曜日)(全国農業会議所)の第8面(地域・農業委員会面)の記事「農林業知らない学生に関心を! ―早大の『農山村体験実習』が人気講座」の中で本書を紹介】
【『南日本新聞』第24961号(2011年6月19日・日曜日)(南日本新聞社)の第7面(特集面)の記事「地方現場に学びの場―早大の人気講座『農山村体験実習』」の中で本書を紹介】
【『岩手日報』第26606号(2011年6月26日・日曜日)(岩手日報社)の第8面「新刊寸評」で本書を紹介】
【『山形新聞』(2011年7月17日・日曜日)(山形新聞社)の地域面の記事「早大生ら農業体験つづる―高畠,寒河江で実習,住民と交流―」で本書を紹介】
【『農業と経済』第77巻・第9号(2011年9月1日発行)(昭和堂)の「ブックガイド」に書評掲載。評者:松原茂仁氏(神戸大学大学院農学研究科地域連携コーディネーター)】
※電子版のご購入にあたっては,各電子書店サイトで詳細をご確認ください:
iBook Store*/アマゾンKindleストア/ebookjapan/GALAPAGOS STORE/紀伊國屋書店/コープデリeフレンズ電子書店/セブンネット/東芝ブックプレイス/VarsityWave eBooks/ひかりTVブック/BooksV/Booklive/honto/本よみうり堂デジタル/楽天Kobo/Reader Store/YONDEMILL
*iPhone/iPadなどのiBooksアプリ、またはiTunes Storeで「早稲田大学出版部」を検索してください。
上野 和昭 著
A5判 576ページ / 本体 9,800円+税
江戸期における京都のアクセント体系および室町期以降のアクセントの変遷について、平曲譜本をはじめとする豊富な資料をもとに明らかにした大作。
第30回新村出賞受賞。
青木 雅浩 著
A5判 440ページ / 本体 8,200円+税
モンゴルにとって1921~1924年は、その後現代に至るまでのモンゴルの基盤がつくりあげられた重要な時期である。この重要な時期に外モンゴルで発生した数々の政治事件について、気鋭のモンゴル近現代史研究者が、モンゴルおよびロシア現地で収集した豊富な史料をもとにその真相を明らかにするとともに、モンゴル近現代史において重要な意義を持つ外モンゴルとソヴィエト、コミンテルンの関係の本質について考察を加えた意欲作。
平成23年度・第6回樫山純三賞受賞。
五十嵐 誠一 著
A5判 510ページ / 本体 8,600円+税
アジア諸国のなかで、いちはやく民主主義体制への移行を果たしたフィリピン。その移行過程においては、市民社会が重要な役割を果たした。民主主義体制への移行過程において、市民社会はどのような役割を果たし、その実態はどのようなものであったか、また市民社会はいかなる手段で民主主義の定着・発展過程に貢献してきたのか。他のアジア諸国との比較も意識しつつ、市民社会の視座から民主化および民主主義の問題を改めて問い直した若き研究者の意欲作。
第10回日本NPO学会優秀賞受賞。
山内 晴子 著
A5判 660ページ / 本体 8,900円+税
朝河貫一(1873-1948)は、日欧の封建制の比較研究で国際的に知られたイェール大学歴史学教授である。彼はどのような歴史学方法論で日本の歴史を欧米知識人に提示し、世界史の中に位置づけたのか。その生涯は日清戦争から冷戦までの激動の時代と重なるが、なぜ日本の危機を予見し、外交のあるべき姿を提示し続けることが出来たのか。朝河が入学後半年で受洗した東京専門学校は、現在想像する以上にキリスト教と関係が深かったのではないか。彼は理想とする「民主主義」を外交理念としたが、どのように体得し、いかなるものであったか。ウォーナーが日米開戦阻止の為に天皇への大統領親書を他の人ではなく、朝河に提案したのはなぜか。朝河が亡くなった時占領軍の横須賀基地では半旗を掲げたというが、彼の戦後構想がこれまで知られている以上に占領軍に影響があったのではないか。本書は、これらの謎を解くために朝河貫一の学者としての生涯を描いた一大叙事詩である。
【『福島民報』第41698号(2010年7月10日・土曜日)の第15面(読書面)「ふくしまの本」に紹介記事掲載】
【『河北新報』(2010年8月23日・月曜日)の第18面(読書・文化面)「東北の本棚」に書評掲載】
【『早稲田学報』1184(2010年12月号)(早稲田大学校友会)の「本と本棚」に書評掲載。評者:山岡道男氏(早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授)】
【『歴史評論』№728(2010年12月号)(歴史科学協議会)に書評掲載。評者:佐藤雄基氏】
【『渋沢研究』第23号(2011年1月)(渋沢研究会編集/渋沢史料館発行)に書評掲載。評者:三牧聖子氏(早稲田大学アジア太平洋研究センター助手)】
【『日本史研究』第584号(2011年4月)(日本史研究会発行)に書評掲載。評者:竹内光浩氏】
【NHK ラジオ第1「ラジオ深夜便」の〔明日へのことば〕 のコーナーに 「歴史学者・朝河貫一に教えられた事」と題して 著者・山内晴子氏が出演(2011年8月16日午前4時台放送)。『ラジオ深夜便』№137(2011年12月号)(NHKサービスセンター)に同内容を再録】
谷川道子・秋葉裕一
A5判 352ページ / 本体 3,200円+税
本書は、日本とドイツ語圏の演劇・演劇文化について、そしてお互いの受容関係について、十名の研究者が書き下ろした論集であり、寄せ集めではなく、相互の内容に働き掛けあい相互の記述を参照しあいながらまとめられたものである。日本とドイツの直接の相互関係は明治維新以降にはじまるが、そこへ至る前史も扱われ、時代、空間、テーマなど、さまざまな「インタラクティヴ」が現われ出る。それぞれの筆者の文体の差は、世代の広がり、問題意識や関心領域の違いをきわだたせるとともに、読者とのインタラクティヴを期待・挑発しているようにも見える。目次には、映画『釣りバカ日誌』や歌舞伎、宝塚歌劇、寺山修司や井上ひさしなど、身近なテーマや人物もならび、ドイツ語圏という鏡にうつして、逆に日本の演劇や文学、文化の姿が見えてくる。
日本図書館協会選定図書。
好評につき、発売直後に重版。
【日本経済新聞2010年5月12日夕刊に紹介記事掲載】
内山 美樹子
A5判 462ページ / 本体 3,500円+税
十世若大夫・八世綱大夫の時代から、国立劇場による通し狂言の成果を経て、越路大夫・津大夫の充実期、国立文楽劇場の開場、吉田玉男の円熟期に至る、文楽のリアルタイムを記録する。2010年3月まで教鞭をとった早稲田大学を退職するにあたっての記念の一冊。
好評につき、発売直後に重版。
【毎日新聞2010年3月7日に書評掲載。評者:渡辺保氏】
【朝日新聞2010年3月12日夕刊に関連記事掲載】
【『クロワッサン』780(2010年5月10日号)(マガジンハウス)の「最近出版されたぜひおすすめの本」で紹介】
【『早稲田学報』1183(2010年10月号)(早稲田大学校友会)の「本と本棚」に書評掲載。評者:飯島満氏(東京文化財研究所無形文化遺産部)】



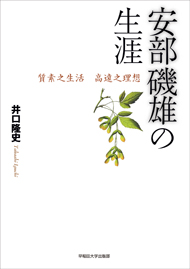


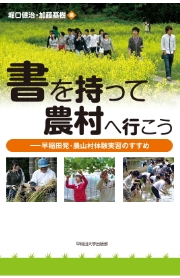




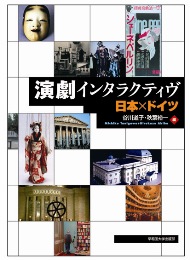
.jpg)