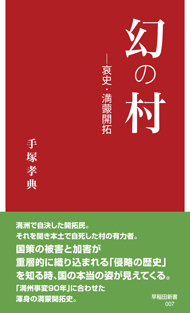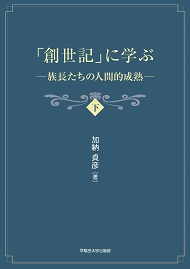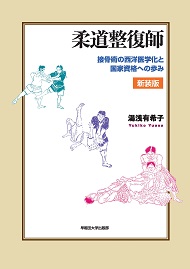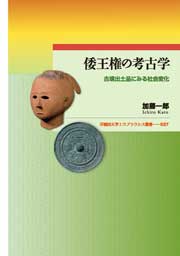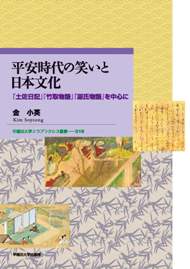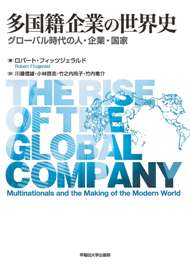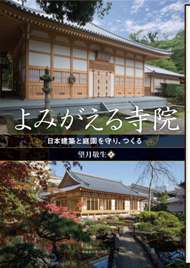ホーム > 歴史・哲学
歴史・哲学
手塚 孝典 著
新書判 210ページ / 本体:900円+税(2021年7月31日発売)
満蒙開拓団の日本人たちは1945 年8 月、ソ連侵攻により満洲(現・中国東北部)に置き去りにされ、集団自決した。
国策に従い彼ら彼女らを満洲へ送り込んだ村の有力者は、それを知り自らも死を選んだ。
時代に踊らされ、時代に流され、時代に殺された人々。時代は国そのものではなかったか――。
著者初の書き下ろしは、村の有力者が書き残した日記を手掛かりに、満蒙開拓の深層、時代と侵略の真相に迫る。
「満州事変90 年」に当たる2021 年の記念碑的ルポルタージュがここに誕生!!! きな臭い日中関係を再考するための糸口が本書に記されている。
加納 貞彦 著
A5判 428ページ / 本体:2,200円+税(2021年6月19日発売)
好評を博した『「創世記」に学ぶ(上)―21世紀の共生』の続編。「創世記」の後半で展開されるイサク、ヤコブ、ヨセフの物語を中心に解説する。古代イスラエルの民の遠い父祖たちである彼らの物語を丹念に読み解き、彼らが人間として成長を遂げ、成熟するに至る歩みに着目する。
人間的な弱さや醜さを引きずり、つまづき転びながら、それでもなおそれぞれの道を歩んでいく族長たちの姿は、現代に生きる私たちにとっても、よりよく生きるためのヒントとなるであろう。聖書を学びたい人、聖書に関心がある人におすすめの一冊。
【推薦のことば】
本書は初めて聖書に接するような人に創世記のそして聖書の面白さを教えてくれる。特に多くの若者に是非勧めたい書物である。――西永 頌(東京大学名誉教授)
将来の不透明さが増しつつあるこの時代、古代イスラエルの民の遠い父祖たちの物語を、本書をひもときながら、一度、じっくり読んでみようではないか。――月本昭男(上智大学神学部特任教授)
湯浅 有希子 著
A5判ソフトカバー 274ページ / 本体:2,800円+税(2021年4月22日発売)
江戸時代から平成にかけての医療および医療制度の分析を通じて、明治以前の「接骨」から大正以降へ続く「柔道整復」への形成過程を明らかにする。柔道整復師の成立に大きな影響を与えた天神真楊流柔術の医学理論および同流柔術家による政治活動のほか、日本柔道整復師会の活動にも言及する。
「本書は、天神真楊流柔術および江戸から平成に至る接骨・柔道整復の医療、制度について、約10年にわたる著者の研究をまとめた歴史書である。『日整六十年史』をはじめ、先人の業績を縦横に博引しながら、自らの見解を新たな柔術伝書、図版、手記、議事録等の実証的な史資料で明解に示し、丹念に分析している。一般にはほとんど知られていない柔道整復の歴史を詳細に描出した労作であり、柔道整復師の手引書として有用な一冊である」公益社団法人日本柔道整復師会会長 工藤鉄男
【出版社からのコメント】
2016年6月の刊行以来ご好評いただいてきた初版本を、このたび使いやすいソフトカバーに替え、お手頃価格の新装版としてお届けします。
加藤 一郎 著
A5判 312ページ / 本体:4,000円+税(2021年3月8日発売)
【第13回日本考古学協会賞奨励賞を受賞!】
日本列島における国家形成期とされる古墳時代、「倭王」の称号が授与された人物が存在し、「倭」の領域を支配する王権構造が機能していた。そこでは、古墳という墓制が活用され、王権構造が生成・維持・発展されてきた。本書では、倭鏡をはじめとする副葬品や埴輪など古墳の出土品を分析し、倭王権の構造や動態、そして古墳時代人の精神世界といった社会史や精神史的な側面について考察する。分析対象を、古墳時代をつうじて生産されていた複数の遺物とし、天皇陵古墳調査の最前線に立つ著者が、古墳時代像を解明する。
大槻 宏樹 著
A5判 436ページ / 本体:2,800円+税(2020年10月10日発売)
他人を頼ることは「悪」なのか。
「自立」が叫ばれるこんにち、高齢者や障がい者など他人に「依存」せざるを得ない人びとがいる。肩身の狭い思いをしながら、社会の片隅にひっそりと生きる人びと。かれらが、胸を張って生きることができる社会へ。
教育学の泰斗が放つ、現代日本への強烈なアンチテーゼ。
加納 貞彦 著
A5判 401ページ / 本体 2,200円+税(2020年4月3日発売)
旧約聖書の「創世記」はだれにも開かれている。そこには、現代の人や社会がよりよくなるためのヒントが詰まっている。著者が半世紀以上にわたり「創世記」を読み続けた成果を伝える。
本書は、特定の宗教・教義にかたよっていないのが特長である。また、聖書原文(聖書協会共同訳『聖書』2018年12月に準拠)を丁寧にあげながら解説を加えているので、原典にいちいちあたらなくても、これ一冊で「創世記」を深く理解できる。
聖書を学びたい人、聖書に関心がある人におすすめの一冊。
推薦のことば
「電子情報通信のすぐれた研究者でありつつ、若き日より聖書に親しみ、聖書に学んでこられた加納貞彦氏が、このたび、創世記の学びを一書にまとめられた。教派や教義にとらわれず、聖書学の成果を生かし、聖書の豊かな思想と現代にも通ずる人生の知恵を平明に読み解いた一冊。」月本昭男氏(上智大学神学部特任教授)
金 小英 著
A5判 322ページ / 定価:4,000円+税(2019年12月18日発売)
『土佐日記』『竹取物語』『源氏物語』をはじめとする中世文学における笑いの表現から、日本文化の特殊性を考察する。気鋭の研究者が独創的視点から迫る、日本文化における「笑い」の原点。
ロバート・フィッツジェラルド 著 川邉信雄/小林啓志/竹之内玲子/竹内竜介 訳
A5判 604ページ / 本体 7,000円+税(2019年12月10日発売)
19世紀から今日まで、5大陸で展開した多国籍企業の活動と、グローバル政治経済秩序の形成と変遷とにその役割を、広い視野と精緻な事例によって分析。
企業と国、政治、外交、軍事との相互作用のなかで、直面した問題をどのように解決してきたのか、現代ビジネスマンが学ぶべき野心的な歴史書。
「本書は、19世紀から現在に至るまでの、世界を駆けたグローバル企業と国家、社会、市場との相互作用を歴史的に精細に分析し、世界経済秩序がなぜ、いかに変化したのかを明らかにしている。GAFAをめぐって新たな国際経済秩序が求められる今日、国際ビジネス人にとって、実際に直面している問題を解決するための強力な指導書と言える。」永田 宏氏(元三井物産株式会社代表取締役副社長)
「我々国際ビジネス人にとって、多国籍企業の使命と役割を広く深く考えさせられる書物である。我々の経済活動の目的が利益の追求だけでないことが、多国籍企業の活動の歴史からいきいきと理解できる。我々は、ビジネスを通し、現地にまた本国にどのように貢献してきのか。本書は歴史的観点から、企業としての使命を我々に今一度振り返らせる啓発書である。」佃 孝之氏(元住友銀行代表取締役専務欧州本部長)
「米中の貿易戦争やBrexitに象徴される世界の現状は、グローバリズムの対極にある自国第一主義や保護主義の蔓延を示している。本書は、グローバル企業の台頭とその後の長きにわたる変遷がいかに世界の国々の経済のみならず、政治や社会、そして国家間の関係やパワーバランスに影響を与えてきたかを広い視野と精緻な事例分析により解明した好著である。」加藤泰彦氏(元三井造船株式会社代表取締役会長)
望月 敬生 著
A4判 233ページ / 本体 3,000円+税(2019年12月5日発売)
全国の寺院・日本庭園の建築、修復、復元に携わり、2017年11月に逝去した望月敬生氏の仕事を紹介。望月氏が携わった全国57の寺院・庭園を迫力あるオールカラー写真でみせるほか、氏作成の建築図面、鬼瓦など細部装飾のスケッチも満載。建築図面の読み方を説明するコーナーも設け、建築の専門知識がない人にも読みやすい。
寺院などの修復・復元に携わる設計者・施工者・研究者、寺院関係者をはじめ、日本の伝統建築を愛するすべての人に捧げる一冊。
「日本建築と庭園の美は人々を魅了し続ける。望月さんはその謎に迫り、よみがえらせた。」中川 武 氏(早稲田大学名誉教授・明治村館長)
張 碧惠 著
A5判 330ページ / 定価:4,000円+税(2019年10月30日発売)
歴史と伝統文化が凝縮した文化遺産である「文物」の破壊・海外流出を防ぐため、国家は何ができるのか―。辛亥革命から台湾へ退去する1949年までの間、中華民国各政府が進めた文物事業の「光と影」に本書は迫る。ナショナリズムと知識人の危機感が追い風となり、文物保護の目的には一貫した方向性があった。法制度も整った。中華民国の人々が「清王朝文物」の価値を発見したとき、強力な権限を持つ専門機関が無かったことから、内部抗争が生じ、保護を有効に進めることができなかった。内憂外患の文物事業に対する考察は、グローバル時代に高まるナショナリズムと文化財の評価・保護の関係から、略奪された文物の返還の在り方までを深く問いかける。