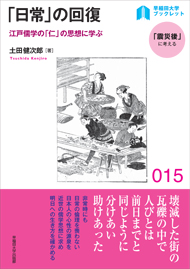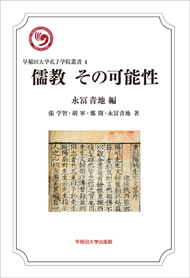ホーム > 歴史・哲学
歴史・哲学
土田 健次郎 著
A5判 / 本体 940円+税 【電子版あり】
壊滅した街の瓦礫の中で,人びとは前日までと同じように分けあい助けあった。非常時にも日常の倫理を喪わない日本人の心性の源泉を,近世の儒学思想に求め,明日への生き方を確かめる。
全国学校図書館協議会選定図書。
【教科書・参考書指定】 早稲田大学文化構想学部・文学部
※電子版のご購入にあたっては,各電子書店サイトで詳細をご確認ください:
iBook Store*/アマゾンKindleストア/ebookjapan/GALAPAGOS STORE/紀伊國屋書店/コープデリeフレンズ電子書店/セブンネット/東芝ブックプレイス/VarsityWave eBooks/ひかりTVブック/BooksV/Booklive/honto/本よみうり堂デジタル/楽天Kobo/Reader Store/YONDEMILL
*iPhone/iPadなどのiBooksアプリ、またはiTunes Storeで「早稲田大学出版部」を検索してください。
黒崎 剛 著
A5判 681ページ / 本体 12,000円+税(2012年3月30日発売)
ヘーゲルの取り組んだ「問題」が未だ解決されていないなか,古典『精神現象学』の現代的意義を明らかにする。従来の文献学的ヘーゲル研究とは一線を画した意欲作。
「筆者の眼からすれば、『精神現象学』は20世紀欧米哲学の諸理論を先取りすると同時に、その近代主義を清算し、概念把握という論理を提供する書でもある。このキメラのような二重性格を持つ謎めいた著作を、存在知のための方法論を確立する試みとして捉え直し、それを通じて現代の社会認識、すなわち非理性的現実のなかでの理性的認識、あるいは私たちの自己認識を可能にする道につなげていくことが筆者のライフワークである。本書は、そのための第一段階として、『精神現象学』の批判だけをその課題とするものである。」
中川 武 +中川研究室 編著
A5判 88ページ / 本体 940円+税 【電子版あり】
長い歴史のなか,東北の人々は津波をはじめとする自然の脅威に幾度となくさらされてきた。東北各地に残る神社仏閣などの建築物,神楽,祭り,伝承の数々。そこに込められた自然との調和の思想――。安全なまちづくりに向けて,いま古人の知恵に学ぶ。
全国学校図書館協議会選定図書。
※電子版のご購入にあたっては,各電子書店サイトで詳細をご確認ください:
iBook Store*/アマゾンKindleストア/ebookjapan/GALAPAGOS STORE/紀伊國屋書店/コープデリeフレンズ電子書店/セブンネット/東芝ブックプレイス/VarsityWave eBooks/ひかりTVブック/BooksV/Booklive/honto/本よみうり堂デジタル/楽天Kobo/Reader Store/YONDEMILL
*iPhone/iPadなどのiBooksアプリ、またはiTunes Storeで「早稲田大学出版部」を検索してください。
川島 京子
A5判 350ページ / 本体 3,500円+税(2012年3月30日発売)
優美さの原点。すべては一人の女性からはじまった。
フランス、ロシア、英国などのバレエ先進国では、国立の養成所があるなどバレエは国家プロジェクトである。一方日本は、民間スクールの奮闘により数多くのスターダンサーを輩出、いまや世界屈指のバレエ大国となった。それはまさに日本の稽古事文化の枠組みにヨーロッパの身体芸術が見事に融合した結果といえる。しかし、この歴史的な快挙が一人の帰化女性により成し遂げられたという事実はあまり知られていない。
ロシア革命により故国を追われ、関東大震災で被災。復興期に日本バレエを立ち上げ、太平洋戦争時の慰問先で客死したエリアナ・パヴロバ(霧島エリ子)。彼女のバレエに捧げた人生は壮絶そのものであった。
著者は、亡命ロシア人エリアナの日本における足跡からロシアでの出自にいたるまでを博捜。精緻な考察,豊富な写真と資料で舞踊史の新たな世界を照らし出す。バレエファンのみならず、すべての日本人に贈る。
日本図書館協会選定図書。
鈴村 興太郎・須賀 晃一・河野 勝・金 慧 著
A5判 100ページ / 本体 940円+税 【電子版あり】
危機における政策が満たすべき条件とは何か。被災者の「日常」を再建し、人々の権利・主体性を大切にしつつ、長期にわたる復興政策を正しくつくりあげるために不可欠の共通理解を探る。経済学・政治学をはじめ、現代の哲学・思想の原点に遡って徹底的に考える。
※電子版のご購入にあたっては,各電子書店サイトで詳細をご確認ください:
iBook Store*/アマゾンKindleストア/ebookjapan/GALAPAGOS STORE/紀伊國屋書店/コープデリeフレンズ電子書店/セブンネット/東芝ブックプレイス/VarsityWave eBooks/ひかりTVブック/BooksV/Booklive/honto/本よみうり堂デジタル/楽天Kobo/Reader Store/YONDEMILL
*iPhone/iPadなどのiBooksアプリ、またはiTunes Storeで「早稲田大学出版部」を検索してください。
永冨 青地 編
A5判 184ページ / 本体 3,000円+税
現代においても輝きを失わない儒教の思想的可能性。殷周期,宋明期,中華民国期,日本の江戸期など,各時代に開花した儒教の多様な可能性を探る一冊。
石濱 裕美子 著
A5判 口絵4ページ 本文334ページ / 本体 7,000円+税
満洲人は,朝鮮人,中国人,モンゴル人が混在する遼東平野を故郷とし,これら歴史ある 3 集団にもまれながら清朝を形成した。そのため,異文化に対して敬意を表することに屈託なく,その摂取についても柔軟であった。
清皇帝は,向き合う集団の文化体系に合わせてその時々に自らの姿を示した。儒教官僚を前にしては儒教思想の説く理想的な王,天子の姿をとり,チベットやモンゴルの仏教徒の前では大乗仏教が理想とする王,菩薩王の姿をとり,満洲人たちの前では八旗の長たるハーンとして君臨した。マルチリンガルな国際人が向き合う集団の言語に合わせて自分の使用する言語を切り替えるように,清皇帝は対する集団の性質に合わせて言語体系や文化的な振る舞いを切り替え,異文化と円滑に交流を行った。
つまり,清皇帝を始めとする満洲人支配層は,満洲語,モンゴル語,漢語,チベット語を程度の差こそあれ理解し,中国文化人であると同時に,チベット仏教徒であり,狩猟に秀でた満洲武人であるという多面的な性格を有していたのである 。これは異文化を外なるもの野蛮なるものとして目下に設定する中国の王権とは対照的な性格である。
本書は,清皇帝が持つ複数の性格のうち,チベット仏教徒に向けて清皇帝が示した姿を様々な側面から解明していくものである。
―本文「はじめに」より
飯山 知保 著
A5判 464ページ / 本体 8,900円+税
6世紀末に端を発し11世紀に制度的に確立した科挙制度は、万人に開かれた栄達の道として、広範な地方知識人層=「士人層」を生み出し、中国社会を規定しつづけてきた。その科挙の歴史の中で絶えず問題とされた南北格差はいかに生まれ、どのような文化的・社会的・経済的意味を持ってきたのか。中国史研究のこの大きなテーマに対し、多くの民族=征服者との接点をなした華北社会の独自の姿に注目し、特に12~14世紀の金代やモンゴル支配の時代に焦点を当てて、南方の漢人社会とは異なる実像を描こうとする雄大な研究。広範な碑刻史料を渉猟し、新しい大量の文献史料を収集・精査して、宋代以降の中華地域における金元時代の意義を問う力作。
青木 雅浩 著
A5判 440ページ / 本体 8,200円+税
モンゴルにとって1921~1924年は、その後現代に至るまでのモンゴルの基盤がつくりあげられた重要な時期である。この重要な時期に外モンゴルで発生した数々の政治事件について、気鋭のモンゴル近現代史研究者が、モンゴルおよびロシア現地で収集した豊富な史料をもとにその真相を明らかにするとともに、モンゴル近現代史において重要な意義を持つ外モンゴルとソヴィエト、コミンテルンの関係の本質について考察を加えた意欲作。
平成23年度・第6回樫山純三賞受賞。
土田健次郎編
A5判 214ページ / 本体 2,800円+税
著しい経済発展を続ける中国において、社会秩序、政治倫理、個人修養などに資するとして、いま儒教が見直されている。韓国では一貫した生命力を維持し、日本でも依然として論語が親しまれるなど、東アジアの社会や文化を考えるうえで儒教は避けては通れない関門である。2500年の歴史を越えて、再び脚光を浴びる儒教を、第一線の研究者が早稲田・ハーバード・北京・清華各大学での成果をもとに問う。
【『中外日報』第27528号(2011年1月25日)の第6面(読書面「中外図書室」)に書評掲載】