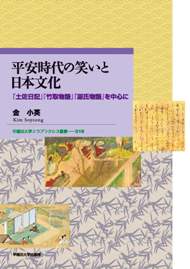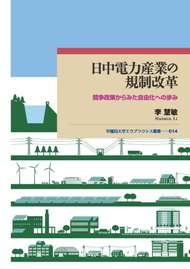ホーム > 早稲田大学エウプラクシス叢書
早稲田大学エウプラクシス叢書
山本 孝司 著
A5判 314ページ / 定価:4,000円+税(2020年1月28日発売)
アメリカで19世紀末から20世紀にかけて起こった、教育改革運動である進歩主義教育において、その源流にいたブロンソン・オルコットの思想を読み解く。オルコットは、個人の尊重を説く超越主義を教育において実践し、のちに「進歩主義教育の父」といわれるようになるフランシス・パーカーや、アメリカを代表する教育思想家ジョン・デューイへ影響を与えたとみられる。アメリカ教育思想史において、超越主義がどのように影響したのか、その思想的水脈を浮き彫りにする。
金 小英 著
A5判 322ページ / 定価:4,000円+税(2019年12月18日発売)
『土佐日記』『竹取物語』『源氏物語』をはじめとする中世文学における笑いの表現から、日本文化の特殊性を考察する。気鋭の研究者が独創的視点から迫る、日本文化における「笑い」の原点。
張 碧惠 著
A5判 330ページ / 定価:4,000円+税(2019年10月30日発売)
歴史と伝統文化が凝縮した文化遺産である「文物」の破壊・海外流出を防ぐため、国家は何ができるのか―。辛亥革命から台湾へ退去する1949年までの間、中華民国各政府が進めた文物事業の「光と影」に本書は迫る。ナショナリズムと知識人の危機感が追い風となり、文物保護の目的には一貫した方向性があった。法制度も整った。中華民国の人々が「清王朝文物」の価値を発見したとき、強力な権限を持つ専門機関が無かったことから、内部抗争が生じ、保護を有効に進めることができなかった。内憂外患の文物事業に対する考察は、グローバル時代に高まるナショナリズムと文化財の評価・保護の関係から、略奪された文物の返還の在り方までを深く問いかける。
酒井 貴広 著
A5判 304ページ / 本体 4,000円+税(2019年6月15日発売)
人はなぜ迷信にとらわれてきたのか――。
かつて高知県内を中心に流布した憑きもの筋の一種、「犬神」。この前近代的な観念が戦後、人々の間で変容していく過程を古老たちへのインタビューや過去の資料分析を通じて解明する。
林 佳恵 著
A5判 306ページ / 本体 4,000円+税(2019年3月25日発売)
古霊宝経研究の新たな可能性を切り開く――。
道教の方向性を教義と儀礼の両面で決定づけた重要な道教経典、古霊宝経。「元始旧経と仙公新経という新旧二系統の霊宝経の存在」というのがこれまでの通説であるが、古霊宝経のテキストを読むかぎり、この考えには実体的根拠がなく、古霊宝経の分類整理を行った劉宋の道士、陸修静の霊宝経観に由来していた。
古霊宝経をありのまま読むと同時に陸修静の功績も振り返る、古霊宝経研究に一石を投じる意欲作。
鄭 東俊 著
A5判 288ページ / 本体 4,000円+税(2019年1月25日発売)
東アジアにおける朝鮮三国(高句麗・百済・新羅)の役割に注目し、その文化要素のうち、特に法制度(律令・中央官制・地方行政制度)を対象に、朝鮮三国に対する中国王朝の影響を分析・検討する。従来の中国王朝を中心とした律令研究に新たな視点を与える。
李 慧敏 著
A5判 318ページ / 本体 4,000円+税(2018年9月5日発売)
かつて電力産業は、日中両国において厳しい政府規制の下に置かれてきた。しかし、近年日本では、発送電分離など規制緩和が進められている。一方、中国はいち早く電力産業の規制緩和に取り組んできたが、自由化への過程は必ずしもうまく進んでいないのが実情である。
日中両国における電力産業自由化の歴史と現状を分析するとともに、電力産業のような寡占産業における事業規制法と競争法の相互関係を考察する。
森 達也 著
A5判 328ページ / 本体 4,000円+税(2018年5月31日発売)
われわれは思想とどのように付き合えばよいのか。
政治的自由論とその批判、価値多元論と自由主義論、ナショナリズムとシオニズム、思想史分野における業績、そして知識人としての人物像……。
英国の政治思想家アイザィア・バーリン(Sir Isaiah Berlin, Order of Merit, 1909-1997)の自由主義思想の特質を明らかにし、全体像を描き出す。
「これまで断片的に語られてきたバーリンの思想の全体像を、「品位ある政治」とシオニズムの相克として浮かび上がらせる。」山本圭氏(立命館大学法学部准教授)が、2018年上半期に出版された書籍の中で印象に残った1冊として紹介(『図書新聞』2018年7月21日号)。
「著者によって、積極的自由と消極的自由というバーリンの隠喩が、一九五八年という文脈を背景として解明された上で、二一世紀のわれわれが生きる分脈において再創造されることを期待したい。」『図書新聞』2018年9月8日号にて紹介。評者:濱真一郎氏(同志社大学法学部教授)。
「初期の哲学研究から自由主義を中心とする政治構想、対抗啓蒙やロマン派に関する思想史研究、そしてシオニズムやイスラエル問題に対する発言まで、バーリンのテキストを入念に検討するだけでなく、バーリン研究の膨大な蓄積、さらには関連する思想動向をも参照するなど、濃密というほかない分析を提供している。」『政治哲学』第25号にて紹介。評者:乙部延剛氏(茨城大学人文社会科学部准教授)。
「本書は、思想家研究でありながら、現代の規範理論への貢献も考慮したものであり、それは、魅力的なリベラリズム解釈の提示と共に、学問研究と現実政治の関係性の考察を追求するものとなっている。」『イギリス哲学研究』第42号(2019年3月)にて紹介。評者:山岡龍一氏(放送大学教養学部教授)。
「アイザィア・バーリンの政治思想の研究。日本語で書かれたものとしては最初の本格的モノグラフといえよう。(中略)バーリンの思想と学問を全体として論じた研究書はこれまでになかった。」『政治思想研究』第19号(2019年5月)にて紹介。評者:松本礼二氏(早稲田大学名誉教授)。
「およそ人文・社会科学における良書とは、議論に決着をつけるものではなく、新たな視座を示し議論を活発化させるものである。本書が多くの読者に読まれ、日本におけるバーリン研究が活性化することを期待したい。」『社会思想史研究』第43号(2019年9月)にて紹介。評者:蛭田 圭氏(オックスフォード大学ウォルフソン・カレッジリサーチフェロー)。
「本書は、思想家バーリンの内面に肉薄しようとする研究である」『ユダヤ・イスラエル研究』第33号、日本ユダヤ学会(2019年12月)にて紹介。評者:市川裕氏(東京大学名誉教授)。
【訂正情報】本書につきましては誤記がございました。お詫びのうえ、下記の通り訂正させていただきます。
『思想の政治学』正誤表(Web用).pdf
柳川 響 著
A5判 口絵+302ページ / 本体 4,000円+税(2018年5月31日発売)
保元の乱に敗れ、37歳の若さでこの世を去った藤原頼長。妥協を知らない苛烈な性格から「悪左府」と呼ばれる一方、「日本一の大学生(だいがくしょう)」と評されるほど、ひときわ優れた学識の持ち主でもあった。
議論が尽くされたとはいいがたい頼長の文人としての顔を遺された資料から明らかにし、その実像を捉え直した意欲作。
水野 忠尚 著
A5判 262ページ / 本体 3,500円+税(2018年3月1日発売)
イギリスのEU離脱、ロシアのクリミヤ半島問題、ウクライナの混乱、シリアをはじめとする中東の混乱、中国の強引な海洋進出、アメリカ・トランプ大統領の誕生、北朝鮮の核問題など、世界の安全保障をめぐる政治体制は不安定化している。
一方、経済面においても、リーマン・ショック、中国経済の減速などに象徴されるように、世界経済はグローバル化の進展とともに不透明感を増している。
こうした混迷する世界政治と世界経済に秩序をもたらす手がかりを与えるのが、アンドレアス・プレデール (1893-1974) が提示した立地論を基礎とした世界経済論である。プレデールは、経済空間と政治(国家)空間の範囲の違いから生ずる諸問題を検討し、経済効率を損なわないためには政治の調整、すなわち国際的な政治的統合が必要であると主張したドイツの経済学者である。その経済思想は、EUなど戦後のヨーロッパ統合のなかにも貫かれている。しかし、有名な学者であるにもかかわらず、日本においてはいま一つ知名度が低い。
本書は、プレデールに関する本邦初の本格的研究であり、混迷する現代に秩序をもたらす手がかりを見出そうとするものである。