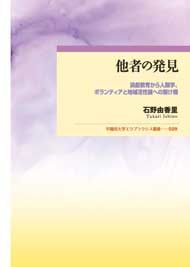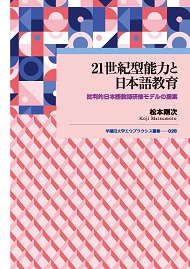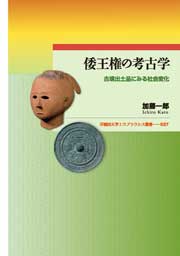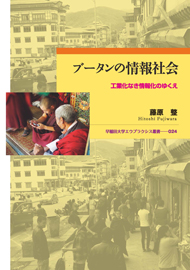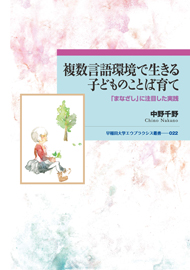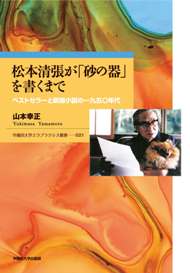ホーム > 早稲田大学エウプラクシス叢書
早稲田大学エウプラクシス叢書
春口 淳一 著
A5判 304ページ / 本体:4,000円+税(2021年10月15日発売)
アフター・コロナを見据えて、大学はいま何をすべきか――。
在籍学生数1,000人足らずの小規模大学に注目し、その留学生政策の実態を検証するとともに、留学生の満足につながることが期待されるエンロールメント・マネジメント(学生が大学に入学し、在学し、卒業するに至るまで、学業面、生活面を大学側がフォローする試み)と日本語教育の役割について考察する。
留学生への教育・支援に携わる大学関係者、必読。
石野 由香里 著
A5判 312ページ / 本体:4,000円+税(2021年6月24日発売)
他者を演じることの持つ力、とりわけ、他者の立場に立つために演じることによる変容を見つめる。俳優としての経験を持つ著者が、役作りの過程で起こる変容は他分野に活かせると実感し、「他者をなぞるように演じる」方法を開発。この手法を授業や日常生活、さらに地域の活動において用いるようになった学生と、その周りの人々の変容の過程をたどる。「相手の立場に立ったつもりになる」のと「立つ」ことの違い、頭で考えるのと実際に身を置いて感じることとはどのように異なるのか。
身体をもって他者をなぞり演じることで、自他の「間(ハザマ)」に立ち、省察を経て自分の主観的なモノの見方の枠組みが変容していくという実践原理を解明し、現代社会の無関心、無理解、対立、差別が問題となる場面への応用可能性を示す。
松本 剛次 著
A5判 312ページ / 本体:4,000円+税(2021年4月23日発売)
21世紀型能力の育成を目指した日本語教育が実践できる教師は、どのように育成するか。
21世紀型能力というものを唱えながら、実際に行われているのはむしろそれとは反対のことではないか。ほかならぬ教師こそが、あるいは教師を教育するものこそが、「新しい」能力、21世紀型能力というものを掲げているにもかかわらず、それとは正反対の旧来型の能力観や価値観を再生産し、強化しているのではないか。
この現状を変え、日本語教育の場で21世紀型能力の教育を真に実現するための日本語教師研修モデルを提示する。
加藤 一郎 著
A5判 312ページ / 本体:4,000円+税(2021年3月8日発売)
【第13回日本考古学協会賞奨励賞を受賞!】
日本列島における国家形成期とされる古墳時代、「倭王」の称号が授与された人物が存在し、「倭」の領域を支配する王権構造が機能していた。そこでは、古墳という墓制が活用され、王権構造が生成・維持・発展されてきた。本書では、倭鏡をはじめとする副葬品や埴輪など古墳の出土品を分析し、倭王権の構造や動態、そして古墳時代人の精神世界といった社会史や精神史的な側面について考察する。分析対象を、古墳時代をつうじて生産されていた複数の遺物とし、天皇陵古墳調査の最前線に立つ著者が、古墳時代像を解明する。
寺﨑 新一郎 著
A5判 292ページ / 定価:4,000円+税(2021年2月10日発売)
【2022年度異文化経営学会学会賞(著者部門)、2022年度日本商業学会賞奨励賞、「日本マーケティング本 大賞2021」準大賞、トリプル受賞!】
グローバル経済を人々の心で読み解く――。
貿易摩擦や規制強化にともなう保護主義的な潮流を背景に、1980年代後半から議論されているカントリー・バイアス(外国に対する先入態度)。国内で初めてカントリー・バイアスを体系的に論じた一書。グローバル化の進展によって外国がより一層身近なものとなる中、すべてのマーケティング研究者、商品等の海外展開に携わるビジネス関係者、必読。
【推薦のことば】
消費者の心理は、国家や文化の違いによって左右される。そうした違いを理解することなく、真のグローバル化に乗り出すことはできない。本書は、多文化社会の認知構造を解明する手がかりを私たちに与えてくれる。――恩藏直人(早稲田大学常任理事・商学学術院教授)
◆「試し読み」できます◆
多文化社会の消費者認知構造.pdf
【寺﨑新一郎氏「日本マーケティング本 大賞2021」準大賞受賞インタビュー】
――本日は宜しくお願いします。まず、今回の受賞作『多文化社会の消費者認知構造』を書かれたきっかけをお聞かせください。
寺﨑 やはり一番のきっかけになったのは、イギリス留学での体験です。
私は、ロンドン大学の修士課程で2年間ほど過ごし、1年目は経営学、2年目は環境・政治とグローバリゼーション学を勉強しました。この2年目のときに、中国やインドといったアジアからの留学生、そして現地のイギリス人など、多様な国々の人々と交流するようになり、その中で、外国や異文化に対する関心がわいてきました。
例えば、ロンドンのピカデリー・サーカス付近にあるチャイナ・タウンによく足を運んでいたのですが、そこで同じ中華料理でもシンガポール風とか、中国のなかでも北方や南方、上海風といった色々な味付けがあることを知りました。
中国や韓国など、日本と政治レベルで対立する国々からの留学生も周囲に多くいましたが、寮で一緒に過ごしていましたし、料理を作ったり、旅行に行ったり、友達として普通に楽しく付き合っていました。
一方でどの留学生も自国民としてのアイデンティティはしっかり持っていました。中国人は中国人、インド人はインド人というアイデンティティがありながら、実際の消費行動はすごくプロアクティブな感じで、興味深いのです。「国としてはあまり好きではないけれど、この国の商品は興味があるので買ってみよう、試してみよう」という人が多かったのが印象的でした。そこで、こうした行動を理論的に捉えられると、より良い消費者理解につながるのではと考えるようになりました。こうした体験が、本を書く動機に強い影響を与えました。

―― イギリス留学を終えて日本に帰国後、早稲田大学大学院商学研究科の博士後期課程に進学されましたね。その後、研究はどのように進められたのでしょうか。
寺﨑 当時はまだはっきりとした研究テーマがなかったので、とりあえず色々な海外ジャーナルのスペシャル・イシューを読み漁りました。主要ジャーナルのスペシャル・イシューを10年分ぐらい表にまとめてみたんです。その中で、学術的なジャーナルではありませんが、『ハーバード・ビジネス・レビュー』で「ディアスポラ・マーケティング」という概念に目が留まったのです。ディアスポラとは平たく言えば移民のことで、ディアスポラ・マーケティングというのは、移民をターゲットにしたマーケティングのことです。私も移民ではありませんが留学をしていたわけですし、これから日本にも移民が増えてくるかもしれない。こうした人々を1つの消費者セグメントとして捉え、マーケティングを考える機会も増えてくるだろうと考えたのです。
それから恩藏直人先生の下、博士後期課程での研究指導を経て、九州大学で助教を務めるようになりました。九州大学箱崎キャンパスの近くは、インド人やネパール人がすごく多くて、JR箱崎駅近くのスーパーマーケットでは多くのエスニックな商品が取り扱われていました。こうした移民の方々も、日本に住んで考え方や価値観が変わるといった、文化変容が恐らく起こっていて、そのうち順応していくのだろうと想像しました。このメカニズムを明らかにしてみてはどうかと着想し、分析的なレンズを探していたところ、「コスモポリタニズム」という概念に出合ったのです。
―― 「コスモポリタニズム」概念に出合ったことが、研究上の大きな転機になったわけですね。そこから、どのように研究を進められたのですか。
寺﨑 日本に住んでいる外国人で、コスモポリタン的志向を持つ人にインタビュー調査をしてみたかったのですが、研究費不足のため、日本人でコスモポリタン志向を持つ人を調査し、どのような過程を経て文化変容が進行したのか研究してみることにしました。本書の第4章から第6章は、このインタビュー調査がもとになっています。
―― インタビューでは、どのような話が聞けましたか。
寺﨑 コスモポリタン志向が高まる背景として、やはり家族からの影響が大きいことが分かりました。お父さんが外国で仕事をしていて、帰国したときに土産話を聞かされたり、お土産をもらったりして外国に興味を持つようになったとか、お母さんが英語教師で、教え子の外国人と交流があって自分も外国に関心を持つようになったとかですね。
一方で、コスモポリタン志向を有する人でも、ナショナリズム的な感情が高まる事例が多くみられました。それがナショナル・アイデンティティの再考という概念の着想につながっています。
このように研究を進めていく中で、体系的なテーマへと昇華させるには入念な研究レビューが必要となってきました。そこで、コスモポリタニズムを大枠で捉えると、どのような概念として位置づけられるのか、関連概念を一通り整理しました。その過程で、消費者の「アフィニティ(好意や愛着)」、「エスノセントリズム(自国中心主義)」「アニモシティ(敵対心)」など、本書で紹介している様々な概念に出合ったのです。
―― 寺﨑先生の研究の面白さは、学術的、理論的な面にとどまらず、マーケティングという実用面に生かせる可能性があることです。そのあたりの意識は、いつ頃から持たれるようになったのですか。
寺﨑 コスモポリタニズムの形成過程の研究をしながら、「コスモポリタン的なアイデンティティを有する人に対して、どのようなマーケティング・コミュニケーションが有効か」という研究に取り組むと、実用面でも有益な示唆が得られると直感しました。そんな時に、2016年に外川拓先生、石井裕明先生、恩藏直人先生が発表された論文で、解釈レベル理論というセオリーを使った実証研究が頭に浮かんだのです。この論文のテーマは、「心理的距離の遠近と対象の捉え方の変化」を検証するものでした。コスモポリタニズムとは、まさに外国や異文化に対する心理的距離を発生させるものであり、こうして生じた距離の遠近に対応したコミュニケーション方略が提案できたら面白いと考えました。
――その後、寺﨑先生は理論を裏付けるべく、実験による実証研究を積み重ねていきます。実験を始めて、手ごたえを感じるようになったのはいつ頃からでしょうか。
寺﨑 2017年2月、京都大学の山内裕先生とシンガポールの南洋理工大学でセミナーを行ったとき、消費者行動研究で著名なジュリアン・カイラ先生に、実験内容を見ていただく機会に恵まれました。そこでカイラ先生から「これはめちゃくちゃ面白いじゃないか」と言っていただいたのです。「こういうタイプのアプローチはあまり見たことがない」と。その時、この研究の方向性は間違っていないと自信が持てるようになりました。

―― 具体的にどのあたりが、カイラ先生に評価されたのでしょうか。
寺﨑 既存のカントリー・バイアス研究の中で心理的距離を扱った研究はなく、こうした課題に正面から取り組んだことが大きかったと思います。ちなみに、心理的距離を扱ったカントリー・バイアス研究は、今でもまだありません。そのこともあってか、このテーマで2021年に発表した私の英語論文はよくダウンロードされているようです。
そこで、書籍中にも度々登場するコペンハーゲン・ビジネススクールのアレキサンダー・ジョシアッセン教授に私の研究論文を送ったところ、カントリー・バイアス研究で実験的な手法を使ってコミュニケーション方略を検討したものはあまりなく、とても面白いと言っていただけました。ジョシアッセン先生は、カントリー・バイアス研究で世界屈指の研究者ですが、これを機にご縁もあって今、共同研究をしているところです。
―― カイラ先生からの激賞後、どのようにして今回の本の出版にこぎつけたのですか。
寺﨑 博士号を取ったら博士論文を書籍化したいという願望は、昔からありました。しかし、以前ある先生から「学術書を出版しようと思ったら、自費出版は普通」と言われたことがあり、収入も少なかったため、出版はしばらく無理だろうと半ばあきらめかけていました。そうしたところ、恩藏直人先生から、「早稲田大学エウプラクシス叢書」という、早稲田大学で博士学位を取得して5年以内の人を対象にしたシリーズが早稲田大学出版部から刊行されているので、それに応募してはどうかとご教示いただいたのです。さっそく応募したところ、無事に採択されました(注―早稲田大学エウプラクシス叢書として刊行するためには、早稲田大学文化推進部が年2回実施している募集に応募し、専門審査員による審査を経て、採択される必要がある)。それで今回、出版することができました。
―― 本の制作過程はいかがでしたか。
寺﨑 原稿のチェックなど想像以上に細かくて、おかげさまで誤字脱字も全く見当たりません。本当に完璧な内容の本が制作できた気がします。校正者からのコメントも細かく、私自身も勉強になりました。表現が間違っていたり、誤字脱字があったりする本をたまに見かけるのですが、この本に関しては心配なく進められました。学術出版を専門とする出版社から上梓できて本当に良かったと思っています。母校の早稲田で出版できたことも、自分の中ではすごくうれしかったです。
早稲田大学出版部の皆様には、本の制作面に加えて営業面でも新聞広告を出していただくなど手厚いサポートがあり、本当に感謝しています。博士号を取得された方がいたら、早稲田大学エウプラクシス叢書での出版をぜひお勧めしたいです。
―― ご本を出版された時の周りの方の反応はいかがでしたか。
寺﨑 「ついに出しましたか」という感じでした。とにかく、すごい勢いでカントリー・バイアス関連の論文を書いていましたので、「いずれ本を出すとは思っていましたが、思ったより早かったですね」と言われることが多かったです。
―― 今回の受賞の報に接したとき、どう思われましたか。
寺﨑 まず、編集担当者の武田さんから「受賞しました」というメールをいただいた時、まったく想定してなかったので、「何だこれは」という感じで、何のメールかなと思いました。メールをよく読んで、こう見て、ああ見て、また上からこう見て、あれっ何か受賞したっぽいなという、そんな感じでした。「やった!」という感じよりも、「あれっ、受賞したのかな。ああ、どうしよう」という感じでした。もちろんうれしかったのですが(笑)。
―― ご家族の反応はいかがでしたか。
寺﨑 妻にメールしたのち帰宅すると、私が意外と落ち着いた様子だったそうで、逆に驚いたようです。きっと、「こんな栄誉ある賞をいただいたのでより一層頑張らなければいけない」という気持ちが芽生えていたからかもしれません。本当にこの分野を究めていかねばという、気の引き締まる思いがしました。

―― 今後、こういうことを研究したい、こういう部分を深めたいという展望がありましたら、お聞かせください。
寺﨑 消費者のアフィニティとアニモシティという、相反する2つの感情がありますが、ある国に対してアフィニティが高い人に加えて、それが低い人にも有効なアプローチを今研究しています。
それを考えるときに実験心理学系の理論、たとえば解釈レベル理論とか、最近だと制御焦点理論が使えることが分かってきました。さっそく『ジャーナル・オブ・インターナショナル・コンシューマー・マーケティング』にその第1弾を発表しました。第2弾を今計画していて、だんだんと知見が深まってきています。今までアフィニティが低い国や、低い人へのアプローチはないものと、諦めるしかなかったのが、実はアプローチできるやり方があることが分かってきましたので、それをグローバルに発信するつもりです。最後は日本語にまとめて書籍化したいと思っています。
―― 研究者志望の人もそうでない人も含めて、これから世に出ていこうとする若い人たちに伝えたいことは何ですか。
寺﨑 東浩紀先生の『弱いつながり:検索ワードを探す旅』(幻冬舎文庫)という本があって、すごく共感しました。今、インターネットで検索すれば何でも調べられるじゃないかという人は多いですが、どういう検索ワードを入れるかという面から考えると、考えつく検索ワードの幅の広さや深さはやはり自分で広げるしかないことに気づきます。その深さとか広さを与えてくれるものはやはり実体験です。その世界に飛び込んでみて、初めて気付くことがある。若いときに現地に足を運んでみたり、それまでいた環境と違うところで過ごしたり、学部の交換留学に参加したりすることで分かることは、たくさんあるはずです。こうした実体験を積み重ねることで、自身の問題意識の幅と深さをどんどん養っていかれると良いと思います。それが研究者にとっても、実務家を目指す人にとっても有効なことだと確信しています。
若いときに研究留学したり、会社で手を挙げて海外に駐在させてもらったり、そういう挑戦が組織にとっても日本にとっても、そして個人の人生にとっても大きく花を開かせてくれるきっかけになるのではないでしょうか。海外に行く機会がなければ、留学生と交流するサークルなどもありますので、積極的に参加されることをお勧めします。
―― 特にここ数年の日本は内向き志向の強い傾向にありますが、そういうことではいけないということですね。
寺﨑 そうです。想像以上に、世界は速いスピードで動いています。今はみんな中国にばかり気を取られていますが、東南アジアも勢いがすごくて、インターネットを活用した様々なビジネスが生まれています。ロンドンにいた時も、マレーシアやインドネシアからたくさんの留学生が来ていました。彼(女)らはすごく優秀で、日本人は到底太刀打ちできないんじゃないかと思うこともありました。マレーシアは多国籍国家ですし、インドネシアにしても様々なバックグラウンドを持った人々が住んでいるので、文化的な適応力は日本人より遥かに上でしょう。こうした人々が海外のネットワークをうまく使ってどんどん活躍していくわけです。
この国をリードしていく人材になりたい、そういう志のある方は、1年でも半年でもいいので、ぜひ海外に行って知見を広げていただきたいですね。
(2021年10月17日、聞き手:編集部 武田文彦)

母校を表敬訪問した時の記念撮影。左から、恩藏直人・早大常任理事、須賀晃一・早大出版部代表取締役社長(早大副総長)、寺﨑新一郎氏、渡邉義浩・早大理事。
岩崎 淳 著
A5判 260ページ / 定価:4,000円+税(2020年11月11日発売)
白川方明・元日銀総裁が推薦!!
「金融規制の国際基準設定に奔走した日銀マンの分析と情熱の書」
「国家とグローバル化した世界の狭間で安定の道筋を明確に示す」
2000年代後半の世界的な金融危機に日銀幹部職員として対応した著者が、国際的な銀行規制見直しの「バーゼルⅢ」策定議論を通じ、世界のグローバル化とG20に代表されるグローバル・ガバナンスを大胆に検証する。グローバル化、主権国家、民主主義の三つを同時に達成することは不可能だという「グローバリゼーションの三重苦」を背景に、グローバル化はグローバル・ガバナンスの正当性向上への要求を高めると結論付ける。特筆されるのは、グローバル金融危機と新型コロナ危機の比較・考察。世界的拡大、経済への深刻な影響、国家が果たすべき役割の再認識、未然防止の失敗などが共通すると指摘する一方、相違点はG20サミットのリーダーシップが発揮されない点を挙げる。金融危機の再発防止措置に倣い、コロナ危機に対しても「グローバルな枠組みによるルール策定が必須」と提言する。
藤原 整 著
A5判 336ページ / 定価:4,000円+税(2020年11月5日発売)
1999年、ブータンではテレビとインターネットが同時に解禁された。高く急峻な山がそびえたつ秘境の国で、どのような近代の情報化への道を辿っていったのだろうか。その足もとには、工業社会を経ずに、情報通信技術の普及が進んでいる、という特異性が広がっている。
グローバル化のなかに、ブータンの情報社会はどのように包摂され得るのか。そして、ブータンというローカルな地域で起きている現象に見られる、新しい情報社会のかたちとは。著者による約10年間のフィールドワークを経て、情報学的世界観や進化史観を背景に、ブータンのいまを見つめる。
佐藤 雄亮 著
A5判 340ページ / 4,000円+税(2020年7月9日発売)
幸福な家庭と理想的世界を結び付け、夢見たレフ・トルストイ。その生涯は、幼い頃死別した母をはじめ、多くの女性たちによって彩られていた。女性たちとの体験は、『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』『見知らぬひと』など数々の名作にどのように反映されているのだろうか。
「女性」はトルストイの博愛主義の原点といえるが、これまでトルストイの女性遍歴はタブー視されてきた。このタブーに果敢に挑み、名作の新たな解釈を試みた画期的研究。
中野 千野 著
A5判 312ページ / 定価:4,000円+税(2020年4月15日発売)
たとえば相手の容姿を見て、先入観や価値観に基づき認識して接する。そこからたち現れる言葉や態度を、相手は「まなざし」として感じとり、自己を形成していく。この「まなざし」論は、哲学をはじめとする、さまざまな領域で論じられてきたが、日本語教育の場では見落とされてきたのではないか。日本語教師である著者は、日本に一度も住んだことのない子どもや、来日した子どもたちが抱える課題に対面し、子どものことばの学びと「まなざし」がどのようにかかわっているのかを考察する。著者自身の論文やエッセイを二次分析し、「まなざし」の形成過程をたどることで、見えてくるものとは。オーストラリアの日本語教室における、教師や保護者が自己省察を行った事例も紹介する。
山本 幸正 著
A5判 300ページ / 本体:4,000円+税(2020年2月10日発売)
清張はいかにして国民的作家になったのか ?!
新進作家が地位と名誉とカネを手に入れ「現代の英雄」になるためには、マスコミの王者といわれた新聞で連載小説をヒットさせるのが近道だった。特に新聞が圧倒的存在感を示した1950年代は、そうであった。清張初の新聞小説「野盗伝奇」(1956年)は、共同通信の配信を通じて地方紙の夕刊に掲載された。新聞小説は掲載が夕刊か朝刊か。地方紙かブロック紙か、それとも全国紙かによって作家の成否を分けたと著者は分析する。読売新聞で1960年に連載が始まる「砂の器」により、清張は「現代の英雄」に大きく近づいた。とはいえ、全国紙から与えられた紙面は夕刊にすぎなかった。1000万人の読者数を誇るのは夕刊ではなく、朝刊だった。
清張が超えなければならない壁は三つあった。一つは、全国紙の朝刊を占めていたベテラン作家たち。残る二つとは…。
小説のうち今も最大の読者数を持つ新聞小説。その新聞小説と作家の深い関係に迫る著者の考察力は、学術書の領域を飛び越え、清張の推理小説に共通するスリリングさと展開力にあふれている。