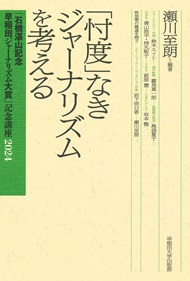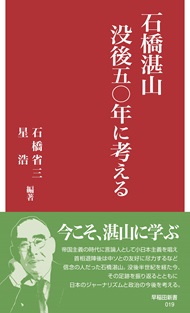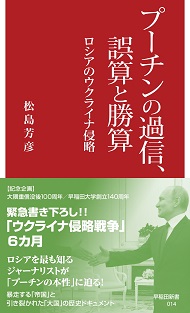ホーム > ジャーナリズム
ジャーナリズム
瀬川 至朗 編著
四六判 248ページ / 本体:1,800円+税(2024年12月13日発売)
権力や権威に屈することなく問題の本質を追うこと、ほかのメディアが報じなくてもニュースを伝え続けること、固定化した社会に諦観せず小さな声に光を当てること――社会を動かしたジャーナリストたちの軌跡をたどる。統一教会と政界の癒着、裁判所の事件記録廃棄問題、PFAS汚染、精神科病院の「死亡退院」、南米アマゾンの「水俣病」、新型コロナワクチンの健康被害、性加害問題において、どのような視点を持ち、取材、調査、報道をしていったのか。早稲田の人気講座「ジャーナリズムの現在」の講義録の最新版。
石橋 省三・星 浩 編著
新書判 250ページ / 本体:900円+税(2023年12月18日発売)
現代日本のジャーナリストは、何を基準とし、誰に向けて、何を発信しようとしているのだろうか。湛山の思想がどう受け継がれてきたのか、また、どう引き継いでいこうとしているのか。以上をテーマに2023年6月17日、早稲田大学大隈記念講堂で開催された石橋湛山没後50年記念シンポジウムを、本書の第一部で採録する。
本書第二部は、より歴史的な観点から石橋湛山の人物と事績について紹介する。湛山と早稲田大学の関係、湛山の経済思想、言論人時代と政治家時代を通じての言論と行動について、気鋭の研究者たちによる論文を掲載。また、湛山の理念を次代のジャーナリストに伝える取組みである「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」についても紹介する。
瀬川至朗 編著
四六判 232ページ / 本体:1800円+税(2023年12月15日発売)
近年注目されている、オープンデータを活用するデータジャーナリズムの最前線がわかる、早大人気講座「ジャーナリズムの現在」の講義録。SNS、統計、衛星画像などの膨大なデータから、どのように分析、調査、取材をしていけばいいのか。調査報道やOSINTの活用事例、ファクトチェックについて取り上げる。さらに、データジャーナリズムの現場を知り、未来を考えるシンポジウムを収録。
そして、これからのジャーナリストに必要な問題意識とは。埋もれた真実に辿り着いた、テニアン島の日本人移民の壮絶な戦争体験、占領期の米軍基地被害、北方領土問題をそれぞれ長年にわたり取材したジャーナリストたちから学ぶ。
瀬川 至朗 編著
四六判 256ページ / 本体:1,800円+税(2023年1月30日発売)
人びとにとって世界を「自分事」にするために、ジャーナリズムはどのような役割を果たすことができるのか。
注目の取材方法OSINTを駆使した調査報道、遠い国で女性たちのために闘う医師の報道を通じて考えるマスメディアの役割、日本の難民・入管問題と外国人取材、ローカル・ジャーナリズム、自然災害報道、国による日本人遺骨の取り違えを暴くキャンペーン報道、特ダネとジャーナリズム、OSINTを駆使したウクライナ報道――ジャーナリストたちはどのような視点を持ち、プロセスを経て、報道に至ったのか。早大人気講座「ジャーナリズムの現在」の講義録、待望の最新版。
松島 芳彦 著
新書判 230ページ / 本体:900円+税(2022年9月2日発売)
ロシア大統領のプーチンが2022年2月24日に始めた「ウクライナ侵略戦争」は誤算が続く。国外逃亡のデマが流れたウクライナ大統領のゼレンスキーは首都キーウにとどまり、専守防衛の陣頭指揮を執る。キーウ制圧を諦め、ドンバス地方の東部戦線に兵力を再編成せざるを得なくなったプーチンに、欧米の経済制裁が重くのしかかる。核兵器の使用を示唆しながらも第三次世界大戦の勃発を巧妙に避ける「皇帝プーチン」に勝算はあるのか――。プーチンが卒業したレニングラード大学で学んだ国際ジャーナリストが、圧倒的取材力・分析力・表現力でもってプーチンの本性、ロシア拡張主義の源泉、欧米の二枚舌外交に迫る歴史ドキュメント。いつ、どこで、なぜ、皇帝が間違ったのかが、この1冊で分かる。
瀬川 至朗 編著
四六判 332ページ / 本体:1,800円+税(2021年12月17日発売)
社会における分断と格差が進むいまこそ、市民の知る権利に応えるというジャーナリズムの機能が問われている。早稲田の人気講座「ジャーナリズムの現在」15回の講義でのジャーナリストたちの言葉には、市民が自由で自律的な社会を築いていくために必要な情報を市民に伝えようとする思いが込められている。隠された公文書、かんぽ生命不正販売、原発事故現場の真実、冤罪がうまれた背景、静かに広がる環境破壊、武漢封鎖における市民の声、沖縄問題のゆくえ――ジャーナリストたちがどのような視点を持ち、プロセスを経て、報道に至ったのか、作品をつくったのかが綴られた一冊。
瀬川 至朗 編著
四六判 366ページ / 本体 1,800円+税(2019年12月10日発売)
「ファクト」を掘り起こす――。
ジャーナリズムとは何か。それはどのような社会的働きをしているのか。ジャーナリストとは誰か。どのような仕事をしているのか。そして、なぜそれをしているのか。早稲田の人気講座シリーズ、待望の最新刊。
「この本は現時点で日本の頂点に立つジャーナリストらが、自らの調査報道で培ったノウハウやテクニック、つまり『個の力』を伝えるとともに、その成果を披露する場である。」
『東奥日報』2020年1月20日.pdf(※本画像は当該ページに限って東奥日報社が利用を許諾したものです)
/
『福島と原発 : 誘致から大震災への五十年』
『福島と原発 2 : 放射線との闘い+1000日の記憶』
『福島と原発 3 : 原発事故関連死』
著者である「福島民報社編集局」の幹部は『福島と原発』の編集後記で、ある地方紙の編集幹部が発した言葉を引用する。2011年度の新聞協会賞選考を巡って「福島民報社編集局」に突き付けられた言葉だ。
「福島はまだ続いている。原発事故はまだ収束していない。原発を誘致した反省、悔いなどはこれから出てくるだろう。その取材・報道を見てから判断したい」
11年度の受賞を逃した福島民報社。東電福島第1原発事故を全社挙げて報道することにより、翌12年度に新聞協会賞に輝いた。『福島と原発』は受賞作の長期連載がベースとなっている。
わたしたちの科学技術文明を崩壊の危機に追い込んだ原発事故が「まだ終わっていない」ことを突き付けてくる。
『福島と原発 2 』と『福島と原発 3』は『福島と原発』の続編。
『震災後に考える : 東日本大震災と向きあう92の分析と提言 』(鎌田薫監修・早稲田大学震災復興研究論集編集委員会編)は、早稲田大学が総力を挙げて取り組む「研究を通じた復興支援」の成果。医療・健康系、インフラ・防災系、都市計画・社会システム系の3分野を柱に、第1部「被災の状況と災害への対応」から第9部「世界の中の東日本大震災」までを通じて92の提言をまとめた。
「ポスト東日本大震災」と「プレ南海トラフ地震」をわが事として捉えるための手引きとなる。
最後にお勧めするのが早稲田大学ブックレット『東日本大震災と憲法 : この国への直言』。
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原則とする「憲法」の観点から、東日本大震災とその後の復旧・復興を考察した力作である。著者の水島朝穂・早稲田大学教授は震災後間もなく、福島県南相馬市から岩手県大槌町まで約800キロを取材した。本書はその体験がベースとなっており、「一憲法研究者である私が、『東日本大震災と憲法』について、歩きながら考え、書き、論じてきた記録である」。大災害を前に、わたしたちの平和憲法は無力であるどころか、大きな可能性を秘めていることを伝える。(俊)
陳 雅賽 著
A5判 288ページ / 本体 4,000円+税(2017年11月10日発売)
国家とメディアの関係はどう変わるのか——。5つの“突発事件”(SARS事件、四川大震災、温州列車脱線事故、天津爆発事故、雷洋事件)報道から検証する。
中国における報道の自由に、ネットメディアはどのような役割を果たしているのか。
「本書は中国メディア研究の学術書でありながらも、中国社会の今後の変化を幅広く考察するうえで多くの素材とヒントを与えてくれる。」2018年3月17日 図書新聞にて紹介。執筆者:藤野彰氏(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院教授)。
早稲田大学ジャーナリズム研究所 編
A5判 460ページ / 本体 2,000円+税(2016年10月5日発売)
戦後70年と戦争経験者、憲法と平和、基地問題、東日本大震災と福島原発事故のいま、記憶に新しい「熊本」の衝撃、足元の政治と社会、進む高齢化、差別の実相と人権、子どもと貧困、教育とスポーツ……。「東京発」ではない、「地方発」の記事群が映し出す「日本の現場」。18紙36本の連載記事を収録。
[協力]北海道新聞、河北新報、福島民報、東京新聞、神奈川新聞、新潟日報、信濃毎日新聞、静岡新聞、京都新聞、山陽新聞、中国新聞、愛媛新聞、高知新聞、熊本日日新聞、宮崎日日新聞、南日本新聞、琉球新報、沖縄タイムス
「どの記事も地元の人々に寄り添い、粘り強く取材しているのが特徴です。また、記者が裏話を語る取材後記も興味深い内容です。全国紙とはひと味違う、日本の真実が読みとれます。」(「図書館教育ニュース」第1421号付録、2016年12月18日)