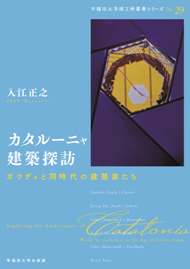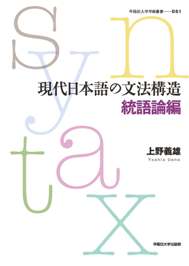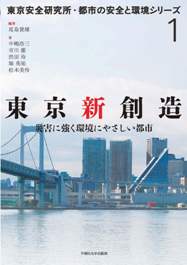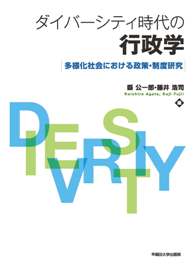ホーム > 新刊案内
新刊案内
入江 正之 著
A5判 オールカラー 182 ページ / 本体 2,000円+税(2017年3月21日発売)
19世紀末、スペインのカタルーニャ地方で興った建築運動、〈カタルーニャ・ムダルニズマ〉。同運動を代表する人物として、わが国ではアントニオ・ガウディが著名である。しかし、ガウディ以外にも素晴らしい仕事を残した同運動の建築家たちは大勢いる。日本ではいまだ知名度の低いかれらのすばらしい仕事の数々を、ガウディ研究の第一人者が40年にわたって現地を訪れ、撮影しつづけてきた貴重な写真とともに紹介する。
上野 義雄 著
A5判 400ページ / 本体 5,000円+税(2017年2月1日発売)
『現代日本語の文法構造 形態論編』の続刊。同書で得られた成果を基に、そこで展開された形態論と対になるべき統語論を描く。
酒井 雅子 著
A5判 326ページ / 本体 4,000円+税(2017年2月1日発売)
自分の頭で広く深く考え、批判的・客観的に判断して行動する人材を育てる教育、クリティカル・シンキング教育。提唱者であるリチャード・ポールおよびマシュー・リップマンの理論を解明しつつ、同教育の実践的方法を提示する。
推薦のことば
「グローバル化、IT(インフォメーション・テクノロジー)化等、社会の変化が著しい。思考力の養成は時代を超えた不易な課題でもあるが、このような多元論理の時代にあって、クリティカル・シンキング教育を新たに開拓していくことは喫緊の課題である。本書はこの課題に、理論的及び実践的に応える大著である。リチャード・ポール及びマシュー・リップマンの理論を解明しながら、クリティカル・シンキングの実践的方法も提示している。」日本国語教育学会理事長、筑波大学名誉教授・桑原隆氏
「本書は、広い知見に基づく学術書である。また、価値の多様化、高度情報化の現代を生きる若者を育てる提言書でもある。自分の頭で、広く深く考え、しかも批判的・客観的に判断して行動できる人材を育てるには、子供の頃から哲学的な教育を行ない、多面的な見方ができるようにするのが必要である。まわりの意見に同調し流されがちな日本人に、この極めて重要な提言である力作の一読を、ぜひお勧めしたい。」東京学芸大学名誉教授・井上尚美氏
尾島 俊雄 編
A5判 176ページ / 本体 1,500円+税(2017年1月25日発売)
生活者にとって魅力ある持続可能な都市とは?
水辺・緑地・風の道があり、安全と福祉を増進する新しい都市のインフラストラクチャーを提言する。
石井 裕晶 編
A5判・上製函入り 口絵4ページ 本文1076ページ / 本体 18,000円+税(2017年1月15日発売)
明治・大正の政財界で活躍した立志伝中の人物、中野武営(なかの・ぶえい)。
明治21年、愛媛県会議長として香川県の独立を成功させたのち、香川県議会議員、衆議院議員、東京市会議長を務める。
政治家として活動する一方、東京株式取引所(現・東京証券取引所)理事長、東京商業会議所(現・東京商工会議所)会頭に就任し、実業界において大正デモクラシーをリードした。
香川新報社(現・四国新聞社)、百十四銀行、高松電灯(現・四国電力)、高松商業会議所(現・高松商工会議所」)といった香川県の有力企業のほか、日本興業銀行(現・みずほ銀行)、明治神宮、理化学研究所の創立に関わる。そのほか、関西鉄道(現・JR東海)社長、東京馬車鉄道(現・東京都交通局)取締役、小田原電車鉄道(現・箱根登山鉄道)社長、日清生命保険(現・T&Gフィナンシャル生命)社長、東洋製鉄株式会社(現・新日鉄住金)社長、田園都市株式会社(現・東京急行電鉄)初代社長も務める。
本書は、中野が新聞・雑誌などに発表した論文、自伝、処世訓を、味わい深い当時の資料の姿をいかしつつ掲載、知られざるその人物像に迫る。明治・大正期の政治・経済史を知るうえで欠かせない資料集。
推薦のことば
「石井裕晶氏は中野の研究者として知られ、『制度変革の政治経済過程』(早稲田大学出版部)で、中野も関わった明治・大正期の営業税廃税運動の論理を極めて緻密に提示した。本書の各章冒頭の解説は、この成果を活かした新鮮な中野小論である。また、収集資料を通して中野の姿が生き生きと浮かび上がる。中野は大隈重信と渋沢栄一を支え、彼らから学び、非植民地・貿易立国論を体現、都市経営にも尽力した。日本近代史研究、とりわけ大隈・渋沢研究等に必読の本だ。」京都大学教授・伊藤之雄氏
「明治から大正にかけて、日清・日露の大きな戦役を経ながら産業国家として発展していったわが国を支えた男の生き様を蘇らせてくれる著作集。中野武営は、高松藩士の家に生まれ、武士としての矜持を持ちながら実業に政治に縦横無尽に活躍した。営業税撤廃といった実業界発展の運動の一方で陸軍の過度な拡大には反対の論陣を張った。また、日米・日清間の親善に務めた。経営者、政治家だけでなく、若い人に広く読んでもらいたい本。」第一生命経済研究所特別顧問・松元 崇氏
島崎 崇史 著
A5判 216ページ / 本体 2,800円+税(2016年12月10日発売)
健康づくりに関する人々への情報提供の方法については、単に情報を提供するだけではなく、本人が自ら行動を変えようと決心し、健康行動を開始・継続・習慣化できるようなアプローチが必要であり、そうした人びとが自発的に健康行動を変容するための心理面からのアプローチをヘルスコミュニケーションという。ヘルスコミュニケーションに関する多様な学問分野における研究および実践の成果を明らかにする。
上野 義雄 著
A5判 396ページ / 本体 5,000円+税(2016年12月10日発売)
統語範疇と形態範疇の峻別、統語構造と形態構造の峻別、屈折と派生の峻別、語や語形の認定、語類の生産性の問題などを中心に、現代日本語の形態論とそれが統語論とどのように関わるのかについての分析を提示する。早稲田大学学術叢書として2014年と2015年に上梓したAn Automodular View of English GrammarとAn Automodular View of Ellipsisで提示した理論的枠組みを日本語の形態論、および日本語の形態論と統語論との接点に関わる諸問題に適用する。
谷口 建速 著
A5判 384ページ / 本体 5,500円+税(2016年11月15日発売)
1996年、中国湖南省長沙市市街地中心部の建築現場で発見された古井中から、総計14万点にのぼる簡牘群(走馬楼呉簡)が出土。この簡牘群は、三世紀(三国呉初期)の長沙郡臨湘侯国に関わる行政文書であった。走馬楼呉簡の地方穀倉や庫に関する記録や簿を主な史料とし、三国呉初期の地方財政制度の構造の解明を試みる。
日本平和学会 編
A5判 194ページ / 本体 2,200円+税(2016年11月10日発売)
改めて、植民地主義と闘う。
絶えず忘却や歪曲の波にさらされてきた植民地支配と植民地主義。
それらは、いま、私たちにどのような影響を与え続けているのか。
植民地主義を精確に捉え、脱植民地主義のための平和学の模索を。
縣 公一郎・藤井 浩司 編
A5判 352ページ / 本体 3,500円+税(2016年10月10日発売)
格差を生み出してきた効率性に偏った社会から脱し、現代の日本社会を多様な価値からなる社会に再生するために、行政は、政治と社会との間で、どのような役割を担うべきか。
個別政策分野の政策研究からのアプローチを中心に、各政策展開を支える制度研究のアプローチも合わせて、社会多様性の再生を考察・展望する。気鋭の研究者たちによる渾身の論文集。
「ゼミなどで学生が特定の政策や制度に興味をもっている場合には、本書を紹介することで多くの学生を満足させることができるであろう。本書によって、行政学的に主題にアプローチするのはどのようにしてなのかということが理解でき、また参考文献も豊富であり、さらなる学習に進んでいくことができる。もちろん研究者にとっても、魅力ある事例の提示によって当該事象について深く考える機会が与えられるであろうし、またここで提供されている理論を自分の研究にも適用してみたいという気にさせられる」 『日本地域政策研究』第18号(2017年3月)(日本地域政策学会)に書評掲載。評者:北山俊哉氏(関西学院大学法学部教授)