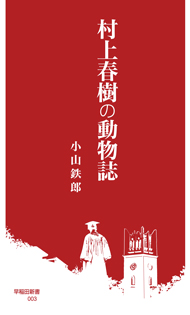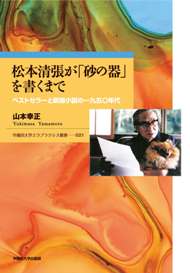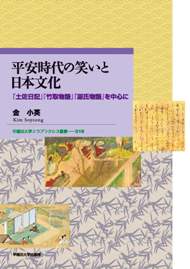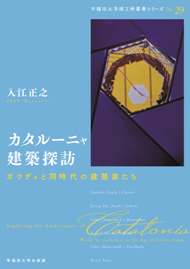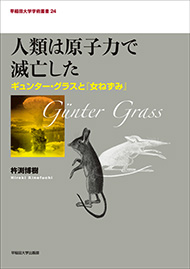ホーム > 文学・芸術
文学・芸術
小山 鉄郎 著
新書判 272ページ / 本体:900円+税(2020年12月10日発売)
村上春樹氏のインタビューを所収!
日本記者クラブ賞に輝いた文芸記者の著者が、動物を手がかりに村上文学の森に深く分け入る 。 デビュー作の『風の歌を聴け』から『猫を棄てる』までを貫く核心のテーマとは 。好評を博した新聞連載記事を大幅加筆した待望の決定版!
【「試し読み」できます】
(試し読み企画)『村上春樹の動物誌』(小山鉄郎著).pdf
◎『村上春樹の動物誌』の担当イラストレーターに聞く――北窓優太さん
小山鉄郎氏の新書新刊『村上春樹の動物誌』でイラストを担当した北窓優太さん(38)=大阪府豊中市在住。新書の章扉にある30点のイラストは、村上春樹氏の深い作品世界にいざなう小山氏の考察に独自のアクセントを付けています。気鋭のグラフィックデザイナーでもある北窓さんに動物のイラストについて、編集部が聞きました。
――動物のイラストとはいえ、村上春樹氏の作品と、それに考察を加える小山鉄郎氏の「双方の世界」をくみ取って描くのは難しかったと思います。
北窓 僕自身、村上春樹さんの本が好きです。20代の頃に熱心に読みました。その読み方が浅いということを、小山さんの原稿を読みながら知りました。動物を糸口に考察を展開しながら、どんどん深くなっていく。重くて深いなあと感じました。
――イラスト制作で注意した点はどこですか。
北窓 村上春樹さんの作品世界を「大陸」と考えるなら、小山さんはその「大陸」の「地図」を作っている。海岸線、河川、平野、山脈などを「地図」に落とし込んでいっている。そして「大陸」のことを理解しようとしている。だから、僕は「大陸」のこと、「地図」のことを念頭に置き、「大陸」と「地図」の関係を忘れないようにしました。小山さんが何千字も使って「地図」を表現しようとするのに対し、僕は一枚のイラストでそれを表現しなければならない。僕の「地図」がピンボケではいけない。そこに難しさと楽しさがありました。
――「新しい発見」があったわけですね。
北窓 小山さんの考察から浮かび上がるイメージ。村上春樹さんの作品から広がってくるイメージ。「双方の世界」を通じて僕の中に湧き上がってくるイメージ。それをイラストに表現することは新しい試みでした。例えば、第十三章の「羊男」。村上春樹さん自らが描いた絵が小説に載っています。まず、村上さんの絵のイメージを壊さず、そして過度に引きずられず、シンボリックで期待感が漂う「羊男」を描きました。実は小山さんの原稿を読むまでは、「羊男」が村上さんにとって「永遠のヒーロー」であることを知りませんでした。20代前半に『羊をめぐる冒険』を僕が読んだ時、「羊男」は物悲しい存在であると理解しました。小山さんの指摘を受けて、ある種の衝撃を受けました。
――北窓さんと同じような「新しい発見」を、イラストを見た読者も味わえるでしょうか。
北窓 小山さんの考察に続いて、僕のイラストを通じても「新しい発見」があるとうれしいです。小山さんは「村上春樹作品は、あらゆる読者の前に開かれている」と言っています。僕のイラストも、読者のイメージを縛ったり、見る人に固定観念を植え付けたりすることがあってはいけないと思います。だから徹底的に、象徴的に描いたのです。村上春樹小説に対する読者のイメージが、僕のイラストからもさらに広がっていくことを願っています。(文責・俊)

「羊男」(Ⓒ北窓優太)

個展会場で『村上春樹の動物誌』の原画(イラスト)を説明する北窓優太氏=東京・神宮前、12月15日午前
【個展の情報】『村上春樹の動物誌』のイラスト全30点の展示を含む北窓優太さんの個展「LIFE & SLUMBER」が12月15日から12月20日まで都内で開かれます。会場は「Popularity gallery & studio」(東京都渋谷区神宮前2-3-24、電話番号 03-5770-2331)で、午前11時から午後7時まで(最終日は午後5時まで)。入場無料。全日、北窓さんが会場に詰める予定です。個展の関連URLはこちら。https://www.popularity.co.jp/about-1
佐藤 雄亮 著
A5判 340ページ / 4,000円+税(2020年7月9日発売)
幸福な家庭と理想的世界を結び付け、夢見たレフ・トルストイ。その生涯は、幼い頃死別した母をはじめ、多くの女性たちによって彩られていた。女性たちとの体験は、『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』『見知らぬひと』など数々の名作にどのように反映されているのだろうか。
「女性」はトルストイの博愛主義の原点といえるが、これまでトルストイの女性遍歴はタブー視されてきた。このタブーに果敢に挑み、名作の新たな解釈を試みた画期的研究。
梅宮 創造 著
四六判 263ページ / 本体 2,500円+税(2020年4月8日発売)
チャールズ・ディケンズ(1812-1870)の風貌のなかでも、ひときわ大きな特徴をなしている部分がある。眼である。あの挑みかかるような大きな眼、異様なばかりに張り詰めた眼の奥には、どこかこの世ならぬ風景がありありと映っていたのだろうか。
「デヴィド・コパフィールド」「クリスマス・キャロル」「オリバー・トゥイスト」など数々の名作を生みだした天才作家。その初期から中期、最晩年に至るまでの試行と試練を、ディケンズ研究の第一人者がたどる。本書末尾では付録として、明治期日本におけるディケンズ受容の実態を、翻訳文の推移と重ねながら紹介する。
19世紀英文学ファン、必読の一冊。
山本 幸正 著
A5判 300ページ / 本体:4,000円+税(2020年2月10日発売)
清張はいかにして国民的作家になったのか ?!
新進作家が地位と名誉とカネを手に入れ「現代の英雄」になるためには、マスコミの王者といわれた新聞で連載小説をヒットさせるのが近道だった。特に新聞が圧倒的存在感を示した1950年代は、そうであった。清張初の新聞小説「野盗伝奇」(1956年)は、共同通信の配信を通じて地方紙の夕刊に掲載された。新聞小説は掲載が夕刊か朝刊か。地方紙かブロック紙か、それとも全国紙かによって作家の成否を分けたと著者は分析する。読売新聞で1960年に連載が始まる「砂の器」により、清張は「現代の英雄」に大きく近づいた。とはいえ、全国紙から与えられた紙面は夕刊にすぎなかった。1000万人の読者数を誇るのは夕刊ではなく、朝刊だった。
清張が超えなければならない壁は三つあった。一つは、全国紙の朝刊を占めていたベテラン作家たち。残る二つとは…。
小説のうち今も最大の読者数を持つ新聞小説。その新聞小説と作家の深い関係に迫る著者の考察力は、学術書の領域を飛び越え、清張の推理小説に共通するスリリングさと展開力にあふれている。
金 小英 著
A5判 322ページ / 定価:4,000円+税(2019年12月18日発売)
『土佐日記』『竹取物語』『源氏物語』をはじめとする中世文学における笑いの表現から、日本文化の特殊性を考察する。気鋭の研究者が独創的視点から迫る、日本文化における「笑い」の原点。
入江 正之 著
A5判 オールカラー 182 ページ / 本体 2,000円+税(2017年3月21日発売)
19世紀末、スペインのカタルーニャ地方で興った建築運動、〈カタルーニャ・ムダルニズマ〉。同運動を代表する人物として、わが国ではアントニオ・ガウディが著名である。しかし、ガウディ以外にも素晴らしい仕事を残した同運動の建築家たちは大勢いる。日本ではいまだ知名度の低いかれらのすばらしい仕事の数々を、ガウディ研究の第一人者が40年にわたって現地を訪れ、撮影しつづけてきた貴重な写真とともに紹介する。
鎌田 薫 監修 早稲田大学震災復興研究論集編集委員会 編
B5判 1024ページ / 本体 6,600円+税(2015年3月25日発売)
「忘れない! 学ぶ! 行動する!」私たちが4年間に考え続けたこと。東日本大震災以後早稲田大学は何を研究し、いかに行動したか。
森 佳子 著
A5判 418ページ / 本体 8,200円+税(2014年6月10日発売)
オペレッタの創始者としても知られるオッフェンバックの音楽は,時代やジャンルの境界を越え,あらゆる国の大衆に求められ,ミュージック・ホールやバレエ,映画などで形を変えて使われ続けた。変幻自在なオッフェンバック芸術の魅力とは何なのだろうか。モダニズム以後ミドルカルチャーの時代に至るまで,常に大衆を魅了し続けた彼の作品を再評価する。
岩佐 壯四郎 著
A5判 560ページ / 本体 10,000円+税(2013年5月31日刊行)
島村抱月が美学理論の体系化の試みにより目指したものとは何か。日本自然主義、近代日本文学を支える思考方法と感性に光を当てる。
杵渕 博樹 著
A5判 324ページ / 本体 6,600円+税(2013年3月30日発売)
核による人類の破滅をテーマにした『女ねずみ』をはじめ一連のグラス作品につき,これまで彼の作品を読んだことがない読者にも易しく解説。